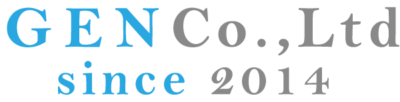放課後等デイサービスとは何で、対象年齢や利用できる子どもは?
放課後等デイサービスとは何か(制度の位置づけ)
放課後等デイサービスは、学校に通う障害のある子ども(就学児)を対象に、放課後や長期休業日に通所で提供される発達支援・生活能力向上支援・社会性育成等の福祉サービスです。
法的には、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の一類型で、同じ枠組みに児童発達支援(主に未就学児向け)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などが含まれます。
自治体(市区町村)が支給決定を行い、指定事業所がサービスを提供し、利用者は原則1割負担(所得に応じた月額上限あり)で利用します。
対象年齢(何歳から何歳までか)
・原則 小学校1年生から高校生相当の「就学児」。
年齢の目安としては、概ね6歳から18歳未満の児童が中心です。
・就学児という考え方 制度上は「学校教育法第1条に規定する学校」(小・中・高・特別支援学校等)に在籍する児童を念頭に置いています。
つまり「学校に在籍しているかどうか」が重要な判断材料になります。
・例外的な取扱い 基本は18歳未満ですが、実務上、個々の事情(進学状況、支援の継続性、自治体の運用方針など)により、在学中の継続利用が調整される場合があります。
詳細はお住まいの自治体の障害福祉担当課に確認するのが確実です。
・未就学児は対象外 小学校就学前の子どもは、原則として放課後等デイサービスではなく「児童発達支援」の利用対象です。
利用できる子ども(対象となる障害・状態)
放課後等デイサービスは、次のような子どもが対象です(いずれも「支援が必要」と自治体が認めた場合)。
・発達障害(ASD、自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害、発達性協調運動障害など)
・知的障害
・肢体不自由、視聴覚障害などの身体障害
・精神障害(小児の気分障害、不安障害などを含むケース)
・重症心身障害、医療的ケアが必要な子(対応できる体制を備えた事業所に限る)
・いわゆるグレーゾーン(診断名が確定していないが、日常生活的・社会的な支援を必要としている)場合でも、アセスメントにより必要性が認められれば支給決定されることがあります
重要な点は、「障害者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)の有無が必須条件ではない」ということです。
多くの自治体で診断書や意見書、発達検査結果、学校の所見などを参考に、総合的に必要性を判断します。
サービスの目的と内容(基本と特徴)
放課後等デイサービスは、単なる「預かり」ではなく、個別の支援目標に基づく発達支援を行うことが義務付けられています。
主な内容は以下のとおりです。
・個別支援計画に基づく支援 アセスメントを行い、家族・学校・関係機関と連携しながら、半年ごと等に見直す個別計画(長期目標・短期目標・到達指標)を作成
・社会性・対人スキル(SST)のトレーニング、集団活動への参加促進
・学習・活動の構造化、注意・実行機能の支援、自己調整(コーピング)スキルの獲得支援
・日常生活動作(ADL)・身辺自立、買い物・交通機関利用などの生活訓練(IADL)
・感覚統合や運動遊び、微細・粗大運動の練習
・高学年~高校生相当では、進路・就労準備(作業体験、職業理解、対人マナー等)
・療育的アプローチ(TEACCH、PECS、ABA的手法の要素など)を取り入れる事業所もある
・保護者支援・ペアレントトレーニング、関係機関連携(学校、医療、相談支援、保健師等)
・送迎(学校→事業所、事業所→自宅など、自治体の運用や事業所体制による)
・提供時間 学校のある日は放課後の2~3時間程度、学校休業日は半日~1日(事業所により異なる)
人員配置と専門性
・必置職種 管理者、児童発達支援管理責任者(個別支援計画の作成・モニタリングの責任者)
・配置が求められる職種 児童指導員、保育士、機能訓練担当職員(OT、PT、STなど)、看護職(医療的ケアに対応する場合)等
・職員研修、事故防止、虐待防止、感染対策、ヒヤリ・ハットの記録など、運営基準に基づく体制整備が義務付けられています
・自己評価・保護者評価の年1回以上の実施・公表が求められ、質の可視化・向上が図られています
利用の流れ(受給者証の取得から開始まで)
1) 相談
・自治体の障害福祉課(子ども家庭課等)や、児童発達支援センター、相談支援事業所に相談
2) アセスメント・計画案
・相談支援専門員が「障害児支援利用計画(計画相談)」を作成(自治体により省略や簡略化の運用あり)
3) 申請・支給決定
・自治体に「障害児通所支援」の利用申請
・必要書類(診断書・意見書、発達検査結果、学校の所見等)は自治体指定に従う
・支給決定が下りると「通所受給者証」が交付され、月あたりの利用上限日数などが記載される
4) 事業所と契約・個別支援計画作成
・見学・体験の上で事業所を選び、契約
・事業所側で個別支援計画(アセスメント含む)を整備し、家族と合意のうえ支援開始
5) モニタリング・見直し
・概ね6か月ごとに支援の効果・到達度を評価し、計画を更新。
学校・医療等との連携会議を行う場合も
費用(利用者負担)
・原則1割負担。
ただし所得に応じた「月額上限」が設定され、多くの世帯では実質的な自己負担は数千円程度に抑えられます(生活保護・低所得世帯は負担なしの区分もあります)
・送迎や特別な材料費等で実費が発生することがあります(事業所規程による)
放課後等デイサービスを選ぶ際のポイント
・支援の質 個別支援計画の具体性、評価(アウトカム)の示し方、保護者・学校との連携姿勢
・職員の専門性 児童発達支援管理責任者の経験、OT・ST等の関与、支援手法の妥当性
・安全・安心 医療的ケア児への対応可否、避難計画、事故時対応、送迎の安全管理
・年齢・特性適合 小学生向け中心か、中高生の進路支援に強いか、特性に合った集団編成がなされているか
・情報公開 自己評価シートの公表、第三者評価の受審状況、加算(強度行動障害支援、看護体制など)の取得状況
よくある質問(対象・要件に関する補足)
・診断が出ていないと使えない?
→必ずしも不可ではありません。
自治体は「支援の必要性」で判断しますが、診断書や専門職の意見が求められることは多いです。
・手帳がないと使えない?
→手帳は不要です。
あれば参考資料にはなります。
・学童保育との違いは?
→学童は子どもの預かり・生活支援が中心、放課後等デイは障害特性に応じた計画的な発達支援が主目的です。
・児童発達支援との違いは?
→児童発達支援は主に未就学児、放課後等デイは就学児向けです。
・18歳を超えたら?
→原則は児童福祉の枠組みを卒業します。
以後は障害者総合支援法に基づく成人向けの日中活動(自立訓練、就労移行、就労継続、生活介護など)の利用を検討します。
高校在学中の移行期は、相談支援専門員と早めに個別に調整を。
法的根拠・参照条文(代表例)
・児童福祉法
— 第4条(児童の定義 満18歳に満たない者)
— 第6条の2(障害児通所支援の定義。
児童発達支援、放課後等デイサービス等を規定)
— 障害児通所支援給付(市町村の支給決定・利用者負担に関する規定。
条文の細部は複数条にまたがります)
・学校教育法第1条(学校の種類を規定。
就学児の範囲を理解する際の参照)
・厚生労働省令「指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
— いわゆる「指定基準」。
職員配置(児童指導員・保育士・児発管等)、設備、安全管理、個別支援計画、送迎等の運営基準を詳細に定める
・厚生労働省通知・ガイドライン
— 児童発達支援・放課後等デイサービスの「ガイドライン」(支援の質の確保・個別支援計画・評価・連携等の運用を示す)
— 支給決定の運用に関する通知(アセスメントの考え方、計画相談の位置づけ、手帳の有無にかかわらない必要性判断等)
これらの根拠により、放課後等デイサービスは「計画に基づく発達支援」「人員・運営基準に即した提供」「自治体の支給決定に基づく利用者負担と上限」の三本柱で制度的に担保されています。
実務上の留意点(自治体差と最新情報)
・支給決定の要件(必要書類、診断の要否、支給量の考え方)、送迎の扱い、利用上限の設定、計画相談の要否などは自治体の運用に差があります。
・医療的ケア児や重度の行動障害がある場合など、対応可能な事業所は限られることがあります。
事前に体制(看護配置、強度行動障害支援研修修了者の有無等)を確認しましょう。
・近年は質の向上に向けた報酬・基準改定が続いており、個別支援計画の実効性や就学後期の移行支援(成人期サービスへの円滑な移行)に重点が置かれています。
最新の改定情報や自治体要綱を確認してください。
まとめ
・放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」で、就学児(概ね6~18歳未満)を対象に、放課後や長期休業日に発達支援・生活訓練・社会参加の支援を行うサービスです。
・対象となる子どもは、発達障害、知的障害、身体障害、精神障害、医療的ケア児など幅広く、手帳の有無は必須条件ではありません。
自治体がアセスメントにより必要性を判断し、受給者証が交付されます。
・サービスは個別支援計画に基づく計画的な療育・訓練が中心で、学校や医療との連携、保護者支援、送迎等も含みます。
・利用には自治体への申請と支給決定が必要で、費用は原則1割負担(所得に応じた月額上限あり)。
自治体の運用に差があるため、必ずお住まいの市区町村の担当窓口で最新の要件・手続を確認しましょう。
根拠(条文・公的資料の例)
・児童福祉法 第4条(児童の定義)、第6条の2(障害児通所支援の定義 放課後等デイサービスを包含)
・学校教育法 第1条(学校の範囲)
・厚生労働省令「指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令。
職員配置・運営・個別支援計画・安全管理等を規定)
・厚生労働省「児童発達支援・放課後等デイサービスのガイドライン」「障害児通所支援に係る支給決定等の運用について(通知)」等
これらの法令・通知に基づいて、対象年齢は「就学児(概ね6~18歳未満)」、対象者は「障害などにより支援が必要と認められた子ども」であることが明確化されています。
制度や運用は改定されることがあるため、最新情報は厚生労働省通知や自治体要綱でご確認ください。
利用開始までの手続きはどう進み、受給者証はどう取得する?
放課後等デイサービス(以下「放デイ」)は、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の一つで、小学生から高校生相当の就学児(発達障害・知的障害・肢体不自由・精神障害・医療的ケア児等を含む)が、放課後や長期休暇中に通所し、療育(発達を促す支援)や生活能力の向上、社会性の獲得、学習・余暇の支援などを受けられる福祉サービスです。
市区町村が支給決定の主体となり、公費負担(原則9割)+利用者負担(原則1割、世帯所得に応じた月額上限あり)で利用できます。
利用には「受給者証(正式には障害児通所支援受給者証、通称 通所受給者証)」が必要です。
放デイの基本と特徴
– 対象
– 発達障害や知的障害等の診断がある児童・生徒、または発達面・行動面に支援ニーズがあり市区町村が必要と認める就学児。
療育手帳等がなくても、医師意見書や所見で認められる場合があります。
– 提供時間と内容
– 平日 放課後〜夕方(例 2〜3時間)
– 休校日・長期休暇 日中(例 4〜6時間)
– 内容 個別の課題学習、生活動作(ADL)・SST(ソーシャルスキルトレーニング)、感覚統合、運動・作業活動、コミュニケーション訓練、集団活動、宿題支援、地域交流、余暇支援など。
事業所によって専門性(学習特化・運動特化・行動支援特化・医療的ケア対応など)が異なります。
– 人員体制(概要)
– 管理者、児童発達支援管理責任者(いわゆる「児発管」 アセスメントと個別支援計画の策定・モニタリングを統括)、児童指導員・保育士・作業療法士・言語聴覚士など。
人員配置・設備・運営は国の基準により定められています。
– 料金(自己負担)
– 原則1割負担。
ただし世帯所得に応じた「月額上限」があり、代表的には以下が目安です(自治体運用・制度改定により変動し得ます)。
– 生活保護・市町村民税非課税世帯 自己負担0円
– 一般1(所得低〜中) 月上限4,600円程度
– 一般2(高所得帯) 月上限37,200円程度
– おやつ代・教材費・行事費等は公費対象外で実費がかかることがあります。
– 複数の福祉サービスを併用しても、同一月の自己負担は「上限額」内に収まるよう「上限管理」が行われます。
– 送迎
– 事業所が学校や自宅まで送迎を行うケースが一般的です(加算算定あり、利用者の別途負担は通常なし。
自治体・事業所により条件あり)。
– 連携
– 学校(担任・特別支援コーディネーター・通級等)、医療、相談支援事業所、保護者と情報共有し、個別支援計画に反映します。
利用開始までの手続きの流れ(標準的なケース)
A. 情報収集・見学
– お住まいの市区町村の障害福祉課(子ども家庭課等)や相談支援事業所、学校、医療機関から情報を得て、希望する放デイを見学・体験します。
– 利用希望日数や送迎可否、専門性、空き状況、費用(実費の有無)、対応可能な特性(医療的ケア・行動上の課題等)を確認します。
B. 相談支援事業所へ連絡(原則)
– 原則として、給付申請には「障害児支援利用計画(案)」が必要です。
指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、ご家庭や学校から聞き取り・アセスメントを行い、目標や利用頻度(週○回、月○日)を整理して計画案を作成します。
– 一部自治体では例外的に「セルフプラン(保護者作成)」を認める運用がありますが、基本は専門職による作成が求められます。
まず自治体窓口に方針をご確認ください。
C. 受給者証(障害児通所支援受給者証)の申請
– 窓口 お住まいの市区町村役場(障害福祉課・子ども家庭支援課等)
– 提出書類(自治体で異なりますが、一般的には)
– 支給申請書(様式は自治体配布)
– 障害児支援利用計画(案)
– 医師の意見書・診断書、または各種手帳の写し(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等)いずれか。
手帳がなくても医師意見書等で申請可のことが多い
– 世帯の課税(所得)状況が分かる書類(課税証明等)または同意書
– マイナンバー・本人確認書類、印鑑
– 利用予定事業所名、希望日数・時間帯 など
– 申請時に自治体担当者が聞き取り・家庭状況確認を行い、必要なら学校や医療機関に照会が入ります。
D. 支給決定(審査〜受給者証交付)
– 自治体が総合的に審査し、利用の必要性・支給量(例えば「月8〜12日」など)・有効期間(多くは6か月〜1年、更新制)を決定します。
– 交付物 障害児通所支援受給者証(通所受給者証)、支給決定通知書、負担上限月額のお知らせ 等。
– 標準的な期間 おおむね2〜4週間程度(書類不備・繁忙期は延びることがあります)。
急を要する場合は相談してください。
E. 事業所と契約・個別支援計画の策定
– 受給者証が届いたら、放デイと面談・重要事項説明・契約を行います。
– 児発管がアセスメントを実施し、受給決定内容・計画(案)を踏まえて「個別支援計画(ISP)」を作成。
保護者へ説明・同意を得ます。
– 送迎経路、学校との連絡方法、緊急時対応、実費費用(おやつ代など)を確認します。
F. 利用開始・モニタリング
– 利用開始後、定期的(概ね6か月ごと)に相談支援事業所が計画のモニタリング・見直しを行い、事業所の個別支援計画も併せて更新します。
– 受給者証の更新時期(有効期間の満了前)には、再申請・支給量の再検討があります。
学校の学年進行や状況変化に応じて調整します。
よくある質問・実務上のポイント
– 受給者証が無いと利用できない?
– 原則として給付対象の利用はできません。
体験利用のみ私費対応の事業所もありますが、継続利用には受給者証が必要です。
– 手帳がないが利用できるか?
– 医師意見書や発達検査所見、学校からの所見などで必要性が認められれば支給決定されることがあります。
自治体の判断により異なるため、まず窓口に相談を。
– 支給量はどう決まる?
– 生活状況・家庭の介護力・学校での様子・医療的ニーズ・長期休暇中の過ごし方などを踏まえ、相談支援計画(案)を基に自治体が決定します。
– 費用の目安
– 自己負担は1割。
ただし月額上限があるため、例えば一般1区分なら月4,600円を超えて請求されることはありません(ただしおやつ・教材・行事等の実費は別途)。
– 事業所選び
– 子どもの特性に合うか(構造化・視覚支援・ABA・感覚統合などの手法、医療的ケアの可否、行動問題への対応)、スタッフの配置・経験、学校との連携姿勢、保護者支援の充実、記録・評価の質(支援記録・アセスメント)、事故防止・虐待防止の体制等を確認しましょう。
受給者証(障害児通所支援受給者証)の取得方法まとめ
– 1) 相談支援事業所へ依頼し、障害児支援利用計画(案)を作る
– 2) 市区町村へ申請(計画案・医師意見書等・課税情報等を添付)
– 3) 自治体の審査・面談を経て支給決定
– 4) 受給者証が交付されたら事業所と契約・利用開始
– 更新時は、モニタリング結果を踏まえて支給量・期間を再決定
法令・制度上の根拠(概要)
– 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
– 放課後等デイサービスは、同法に基づく「障害児通所支援」の一類型として位置づけられ、市町村が支給決定の主体であること、利用者負担(原則1割)や利用給付の仕組み、指定事業者制度等の基本枠組みが定められています。
– 児童福祉法施行規則・省令(厚生労働省令)
– 指定障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の人員・設備・運営基準、記録・個別支援計画の作成義務、児童発達支援管理責任者の配置等に関する詳細基準が規定されています。
– 厚生労働省告示・通知(ガイドライン)
– 放課後等デイサービスの運営・支援内容の質の向上に関するガイドライン、アセスメント項目、計画・モニタリング・評価の考え方、学校・医療等との連携、虐待防止・事故防止等の留意事項が示されています。
– 市区町村の要綱・運用
– 申請様式、必要書類、セルフプランの可否、医師意見書の取扱い、支給量の標準、更新手続などの具体運用は自治体要綱・実施要領で定められています。
実務のコツ
– 早めに動く 新学期や長期休暇前は混み合います。
見学→計画→申請→交付に1〜2か月程度みると安心です。
– 学校情報の活用 担任や通級担当からの所見・配慮事項は支援の必要性の説明に有用です。
– 医療機関との連携 診断書・意見書は支給決定の重要資料です。
予約待ちが長い場合は早めに依頼を。
– 計画は具体的に 週○回、放課後○時〜、長期休暇は○日など具体の頻度・時間を計画案に記すと審査がスムーズです。
– 実費の確認 おやつ・教材・活動費の目安、キャンセル規程、送迎条件を契約前に必ず確認。
– 上限管理の指定 複数事業所を使う場合は「上限管理事業所」を決め、自己負担上限を超えないよう管理してもらいます。
最後に
放デイは、家庭・学校・医療・地域をつなぎ、子どもの発達と家庭の生活を支える大切な社会資源です。
制度は全国共通の枠組みがある一方、申請様式や運用は市区町村ごとに差があります。
まずはお住まいの自治体窓口と相談支援事業所に連絡し、具体的な必要書類・手順・スケジュールを確認のうえ進めると確実です。
参考(制度の根拠に関する公的情報の例)
– 児童福祉法(障害児通所支援の規定)
– 児童福祉法施行規則・指定障害児通所支援の人員・設備・運営基準(厚労省令)
– 厚生労働省「放課後等デイサービス ガイドライン」「障害児通所支援の手引き」等の通知・事務連絡
– 各自治体の「障害児通所支援事業実施要綱」「受給者証交付要綱」
これらの法令・通知は厚生労働省やe-Gov法令検索、自治体公式サイトで公開されています。
制度・金額等は改定されることがありますので、最新情報を必ず自治体窓口でご確認ください。
どんな支援内容や1日の流れがあり、学童保育や児童発達支援とどう違う?
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービス(通称 放デイ)は、学校に就学している障害のある子ども(おおむね小1〜高3相当の年齢の児童)を対象に、放課後や長期休暇中に通所で提供される福祉サービスです。
児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の一類型で、療育(発達や行動の特性に応じた支援)や生活スキルの獲得、社会性の向上、余暇の充実、家族のレスパイト(介護負担の軽減)などを目的にしています。
教育サービス(学校)でも、医療保険のリハビリでもなく、「福祉サービス」に位置づく点が基本です。
法的根拠・対象
– 根拠法令 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援(2012年の制度再編で創設)。
厚生労働省の指定・監督のもと、市区町村が支給決定・給付を行います。
– 対象年齢・属性 原則として就学児(小学生〜高校生相当)。
障害種別は、発達障害、知的障害、肢体不自由、医療的ケア児等を含みますが、医療的ケアが必要な場合は看護配置や個別対応力のある事業所を選ぶ必要があります。
– 事業所基準 管理者、児童発達支援管理責任者(いわゆる「児発管」)、児童指導員・保育士・教員免許保有者等の配置、面積・安全・感染対策等の設備、運営ルール(個別支援計画の作成・モニタリング、学校や関係機関連携等)が定められています(厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」等)。
利用開始までの流れ(基本)
1) 相談 まず市区町村窓口または障害児相談支援事業所に相談。
お子さんの状況や利用目的を整理します。
2) 申請 市区町村に障害児通所支援の支給決定を申請。
医師の意見書・障害者手帳等の有無、学校や家庭の状況などが考慮されます。
3) 支給決定 利用日数(支給量)と期間が決まると「通所受給者証」が交付されます。
4) 事業所選定・契約 見学・体験後、事業所と契約。
児発管がアセスメントを行い「個別支援計画」を作成します。
5) 利用開始 計画に沿って通所。
定期的にモニタリング・サービス担当者会議を行い、目標や支援内容を見直します。
費用(利用者負担)
– 原則1割負担ですが、世帯の所得区分に応じた「利用者負担上限月額」が適用され、多くのご家庭では月額の上限(例 0円/4,600円/37,200円の三区分)が設定されます。
おやつ代・昼食代・教材費・外出費等の実費は別途かかることがあります。
– 詳細は各市区町村の案内に従ってください(障害児通所支援の利用者負担は自治体の告示・要綱で具体化されています)。
主な支援内容(特徴)
– 個別療育 言語・コミュニケーション、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、注意・遂行機能、感覚統合的アプローチ、微細・粗大運動、学習の土台づくりなど。
作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)等の専門職が関わる事業所もあります。
– 集団活動 ルールのある遊び、協働活動、買い物学習、外出・地域参加、クラブ活動等を通じた社会性・対人スキルの向上。
– 生活スキル・自立支援 身辺自立(身支度、清潔、金銭管理の基礎)、公共交通機関の利用練習、時間管理、家庭学習の取り組み方。
– 学校・家庭との連携 連絡帳、支援会議、学校訪問や保育所等訪問支援との連携により、家庭・学校・事業所で一貫性のある支援を図ります。
– 保護者支援 ペアレントトレーニング、相談支援、進路・福祉制度案内、きょうだい支援の工夫など。
– 送迎 学校→事業所→自宅の送迎を実施する所が多く、長期休暇中は自宅↔事業所送迎が一般的です(提供範囲は事業所ごとに規定)。
1日の流れ(例)
– 学校授業日
1) 学校迎え→来所、健康チェック・連絡帳確認
2) 個別課題(10〜30分)…コミュニケーション課題、作業課題など
3) 集団活動(30〜60分)…SST、ルール遊び、運動・感覚活動
4) おやつ・休憩
5) 宿題や学習サポート、生活スキル練習(片付け、翌日の準備)
6) 振り返り(今日できたことの可視化)→順次送迎・帰宅
– 学校休業日(夏休み等)
1) 朝送迎→体調確認
2) 個別・小集団での課題
3) 昼食(持参または提供)、食事マナー練習
4) 外出・地域活動(公園、図書館、買い物学習等)または長めのプログラム
5) 片付け・帰りの会→送迎
– 所要時間 授業日で2〜3時間、休業日で4〜6時間程度が目安(事業所や自治体加算要件により幅があります)。
学童保育(放課後児童クラブ)との違い
– 目的・法的枠組み
放課後等デイサービス 児童福祉法に基づく障害児通所支援。
療育・発達支援・家族のレスパイトが中心。
学童保育(放課後児童クラブ) 児童福祉法に基づく「放課後児童健全育成事業」。
保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生の「生活の場」を提供し、遊び・生活支援を通じて健全育成を図る。
– 対象
放デイ 障害のある就学児(支給決定と受給者証が必要)。
学童 原則すべての小学生(障害の有無は問わない。
自治体や運営主体によって受け入れの配慮・加配の有無は異なる)。
– 支援中身
放デイ 個別支援計画に基づく療育、SST、感覚・運動、行動課題への専門的支援、学校・医療・福祉との密な連携。
学童 安全な居場所の提供、遊び・生活支援・宿題見守りが中心。
療育・機能訓練の提供は制度上の想定外。
– 職員配置・資格
放デイ 児童発達支援管理責任者、児童指導員・保育士等を配置。
リハ専門職の配置加算など専門性の要件や評価がある。
学童 放課後児童支援員を2名以上配置(うち1名以上は資格要件を満たす支援員)。
定員や面積は運営指針で基準化。
– 料金・手続
放デイ 障害児通所支援の給付で原則1割負担+月上限額あり。
利用には市区町村の支給決定・受給者証が必須。
学童 自治体が定める利用料(月額制が一般的)。
受給者証は不要。
所得に応じた減免制度は自治体ごとにあり。
– 利用時間
放デイ 放課後〜夕方、休業日は日中のプログラム。
送迎ありの事業所が多い。
学童 授業終了後〜夕方(19時前後)まで、休業日は朝から夕方までの長時間開所が多い。
児童発達支援との違い
– 位置づけ いずれも児童福祉法上の障害児通所支援。
ただし、児童発達支援は未就学児(0〜6歳)を対象とした早期療育、放課後等デイサービスは就学児を対象とした放課後・休業日支援。
– 支援のねらい 児童発達支援は就園・就学へ向けた基礎発達の促進と親子支援が中心(親子通所が多い)。
放デイは学校生活・地域生活・将来の自立や就労準備につながるスキル獲得、余暇の過ごし方の学習が中心。
– 利用時間・連携 児童発達支援は日中帯(保育所・幼稚園と連携)、放デイは放課後・長期休暇中(学校・学年担任・特別支援コーディネーター等と連携)。
– 移行 就学時に児童発達支援から放デイへ移るケースが多く、情報共有・計画の継続性が重要。
選び方のポイント
– 個別支援計画の質 アセスメントの丁寧さ、到達指標(数値・観察記録)の明確さ、家庭・学校場面へ汎化する工夫があるか。
– 職員体制と専門性 児発管の経験、児童指導員の研修歴、OT・ST・心理職の関与、強度行動障害支援研修の修了者の有無など。
– 学校・関係機関連携 担任や校内委員会との情報共有、保育所等訪問支援との併用ノウハウがあるか。
– 環境と安全 構造化(視覚的手がかり、スケジュール提示)、感覚過敏への配慮、避難計画や事故防止策。
– 送迎・開所時間 家庭の生活リズムと合うか、長期休暇中の運営体制。
– 費用の透明性 実費(おやつ・教材・外出費)の明示、キャンセル規定。
– 合同・集団編成 年齢や特性の近い子で小集団を組めているか、過密になっていないか(定員10名前後を上限に運営する所が多い)。
よくある誤解と注意点
– 医療行為は原則不可 経管栄養・吸引などの医療的ケアは、看護師配置や医療的ケア児の受け入れ体制がある事業所でのみ対応可。
– 学習塾ではない 宿題支援は行いますが、学習塾のような成績向上を直接目的とした指導は制度の想定外。
学習の土台(注意・作業耐性・手順理解など)を整える支援が中心。
– 乱立と質の差 近年、事業所数が増え、質に差があると指摘されています。
見学・体験・第三者評価・自己評価表の公開内容を必ず確認しましょう。
根拠・参照できる公的資料
– 児童福祉法(障害児通所支援の規定) 放課後等デイサービス・児童発達支援の法的根拠。
市区町村の支給決定、利用者負担の仕組み等が定められています。
– 厚生労働省「放課後等デイサービス ガイドライン」(2017年策定、以後改訂) 事業所が備えるべき質の指針(アセスメント、個別支援計画、モニタリング、家族支援、関係機関連携、自己評価・公開など)。
– 厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」 未就学児向け療育の基本的考え方と運営の質指標。
– 厚生労働省「放課後児童クラブ運営指針」(学童保育の基準) 目的、職員配置、面積、運営時間等の基準。
放デイとの制度的違いの根拠。
– 利用者負担の上限月額 障害児通所支援に関する厚生労働省通知および各自治体の実施要綱(世帯所得区分に応じた0円/4,600円/37,200円などの上限設定)。
– 自治体の指定・監査情報、第三者評価、事業所の自己評価表(毎年度の公表が求められています)。
まとめ
– 放課後等デイサービスは、就学している障害のある子のための「福祉の療育サービス」。
学校の放課後や休業日に、個別計画に基づき、発達・行動面、生活スキル、社会性、余暇の過ごし方を支えるのが役割です。
– 学童保育は「居場所・生活の場」を提供する健全育成事業で、療育を目的としない点が制度上の大きな違いです。
– 児童発達支援は未就学児向けの早期療育で、放課後等デイサービスは就学児向け。
就学時にスムーズな移行と連携が重要です。
– 利用には市区町村の支給決定と通所受給者証が必要。
費用は1割負担に上限月額があり、多くの家庭で実負担は限定されます。
– 事業所ごとに専門性や運営の質に差があるため、複数の見学・体験、個別支援計画の中身、他機関連携の実績、自己評価の公開状況まで確認することをおすすめします。
必要であれば、お住まいの自治体名を教えていただければ、手続き窓口や上限月額、事業所検索の方法(福祉情報ポータル等)を具体的にご案内します。
利用料金や自己負担はいくらで、利用日数・送迎などの利用ルールは?
放課後等デイサービス(以下「放デイ」)は、障害や発達に特性のある就学年齢(小学生〜高校生相当)の子どもが、放課後や学校休業日に通い、生活動作・社会性・学習の基礎・コミュニケーションなどの力を伸ばすための「障害児通所支援」です。
児童福祉法にもとづく公的サービスで、自治体の支給決定と受給者証(通所受給者証)が必要になります。
ここでは、利用の基本、特徴、利用料金(自己負担)、利用できる日数や送迎などのルールを体系的に解説し、根拠となる法令・通知も示します。
放課後等デイサービスの基本と特徴
– 目的・対象
– 学校終了後や長期休業日に、療育的な支援や生活・社会参加の練習機会を提供し、家庭・学校・地域での暮らしを支えることが目的です。
– 対象は原則として就学年齢の障害児(身体・知的・精神・発達障害など)。
障害者手帳がない場合でも、医師の意見や発達検査、保護者・学校の情報等を踏まえ、自治体が必要性を認めれば支給決定されることがあります。
– サービス内容の例
– 個別支援(SST・コミュニケーション練習、感覚統合、行動の見通し、ライフスキル)
– 小集団活動(協働・役割分担・ルール理解、運動遊び、制作、社会体験)
– 学習の基礎(学習の土台づくりや学習環境の調整)
– 保護者支援(ペアレントトレーニング、相談、関係機関連携)
– 送迎(後述)
– 事業所の人員・運営の基準(概要)
– 管理者、児童発達支援管理責任者(個別支援計画を統括)、児童指導員・保育士等の配置が義務付けられています。
– 定員や職員配置、記録・計画作成、安全衛生、虐待防止、利用者・保護者への説明(重要事項説明)などの運営基準が省令・通知で整備されています。
– 利用までの流れ(標準)
1) 相談(自治体窓口や相談支援事業所、児童発達支援センター等)
2) 障害児支援利用計画の作成(相談支援専門員)
3) 自治体に申請→支給決定→受給者証交付(支給量=月あたりの日数等が記載)
4) 事業所見学・契約(重要事項説明書の確認)→利用開始
利用料金・自己負担はいくら?
– 基本の考え方
– 利用料(事業所に支払われる報酬)は公費9割+利用者1割の原則ですが、世帯の所得に応じた「利用者負担上限月額」があり、同一月内に利用した障害児通所支援(放デイ・児童発達支援等)の自己負担合計は、その上限額を超えて支払う必要はありません(上限管理は事業所間で調整されます)。
– 代表的な上限月額の区分(子ども・障害児通所支援)
– 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 上限0円
– 市町村民税課税世帯(一般1) 上限4,600円/月
– 一定以上所得の世帯(一般2) 上限37,200円/月
備考 どの区分に当てはまるかは、世帯の住民税(所得割)等で判定します。
年収の目安表示が自治体資料に載ることもありますが、家族構成や控除により異なるため、最終的には自治体の判定が基準です。
– 具体的な支払いイメージ
– 例 月12日利用しても、世帯区分が「一般1」なら自己負担は月4,600円が上限。
これには同月内の他の障害児通所支援の自己負担も合算されます。
– 世帯区分が非課税なら、自己負担は0円(ただし実費は別途かかる場合あり)。
– 自己負担以外にかかり得る実費
– おやつ代や教材費、社会体験の入場料、外出時の公共交通機関費用、給食(昼食)・弁当代等は「実費」として別途徴収されることがあります。
金額や徴収の有無は事業所ごとに異なり、重要事項説明書に明記されます。
– 実費徴収は「提供した実費相当」であり、利用料の上乗せのような一律徴収は認められていません。
利用日数・時間、利用ルールは?
– 利用できる日数(支給量)
– 全国一律の日数上限はなく、自治体が個々の状況(学校の時間割、家庭の養育状況、他サービスの利用、子どもの支援ニーズ等)を踏まえて、月あたりの支給量(日数)を決定します。
受給者証に記載された支給量の範囲内で、事業所と調整して通所します。
– 目安としては週2〜5回程度で決定されることが多いですが、あくまで個別判断です。
長期休業中は平日昼間の長時間利用が可能な計画となることもあります。
– 1日の提供時間
– 学校のある日は、放課後から数時間(例 2〜3時間程度)が一般的。
学校休業日は、午前〜午後の長時間(例 4〜6時間程度)を設定する事業所が多いです。
正確な時間帯・カリキュラムは事業所ごとに異なります。
– 併用のルール
– 同一時間帯に複数サービスを同時利用することはできませんが、曜日・時間を分けて複数の放デイや、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援などと併用することは、支給計画に沿って可能です。
自己負担は同月内で合算して上限管理されます。
– キャンセルや欠席
– 欠席時に利用料(自己負担)を請求することはできません。
ただし、すでに発生してしまった外出イベントのチケット代など、実費のキャンセル料相当を求められる場合があります。
事業所の規程(重要事項説明書)を事前に必ず確認しましょう。
– 利用契約・運営ルール
– 送迎の有無・範囲、活動内容、実費、緊急時の対応、個人情報の取扱い、虐待防止、苦情対応などは、契約前に書面で説明(重要事項説明)され、保護者の同意が必要です。
– 事業所は個別支援計画を作成し、定期的にモニタリング・見直しを行います。
保護者・学校・関係機関との連携も運営基準上求められています。
送迎(ピックアップ・見送り)の取り扱い
– 送迎の位置づけ
– 放デイでは、学校や自宅と事業所間の送迎を行う事業所が一般的です。
送迎の有無や対象エリア、時間帯、条件(例 道路事情・安全基準・保護者同乗の可否等)は事業所が定め、契約時に明示します。
送迎は義務ではなく、事業所の体制や安全管理上の判断で提供されます。
– 費用
– 通常の通所のための送迎は、基本的に利用料に含まれる取扱いで、送迎そのものに対して追加の自己負担を求めないのが原則です(別建ての「送迎料」を徴収しない)。
ただし、公共交通機関を用いた外出活動などの「支援とは別の実費」は、実費として徴収されることがあります。
– 安全管理
– 車両の安全性、チャイルドシート等の装備、送迎記録、引き渡し手順、緊急時連絡体制など、安全確保のための手順が求められます。
悪天候や災害時は送迎を中止・変更する場合があります。
根拠(法令・通知等の概要)
– 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
– 放課後等デイサービスは、同法に基づく「障害児通所支援」の一類型です(定義・位置づけは同法の障害児支援に関する規定に明記)。
– 自治体による支給決定、受給者証の交付、支給量(利用日数等)の決定手続、支援の内容・目的が規定されています。
– 児童福祉法施行令・施行規則、厚生労働省令
– 「指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」により、職員配置(児童発達支援管理責任者、児童指導員・保育士等)、記録・計画(個別支援計画)、安全管理、苦情対応、説明義務等が定められています。
– 「障害福祉サービス等の利用者負担に関する基準」(厚生労働省令)および関連通知
– 利用者負担の原則(1割)と、所得に応じた「利用者負担上限月額」(子どもは0円/4,600円/37,200円)を規定。
世帯の住民税等で区分を判定し、同月内の合算・上限管理を行うことが示されています。
– 報酬・運営に関する通知・告示(厚生労働省)
– 令和6年度(2024年度)障害福祉サービス等報酬改定関係資料や、障害児通所支援の運営に係る留意事項通知において、送迎の在り方、実費徴収の考え方、欠席時の取扱い、連携・記録・評価などの詳細が示されています。
– 自治体要綱・実施要領
– 具体の申請手続、判定基準、支給量の決定方針、地域独自の加算・減免や送迎エリアの目安などは、自治体が要綱・実施要領等で定めています(各市区町村の公式サイトや窓口で公表)。
よくある質問と実務上の留意点
– 手帳がないと利用できない?
– 必須ではありません。
医師の意見書や発達検査結果、学校からの情報等をもとに、自治体が支援の必要性を認めれば支給決定されることがあります。
– 実費はいくらぐらい?
– おやつ代は1日50〜200円前後、外出時の交通費・入場料は実費、昼食が出る場合は数百円〜数千円/回など、事業所と活動内容により幅があります。
契約前に金額・徴収条件を必ず確認してください。
– 上限月額は毎年変わる?
– 区分や金額は制度改正で見直される可能性があります。
最新の上限額や判定基準は自治体・厚生労働省の最新資料で確認を。
– 送迎は必ずしてもらえる?
– 義務ではありません。
送迎の可否・範囲・時間は事業所の体制と安全基準によります。
居住地や学校の位置により送迎対象外の場合もあるため、契約前に確認が必要です。
– 何日くらい通える?
– 子ども・家庭の状況により個別に決まります。
希望日数がある場合は、相談支援専門員に具体的な根拠(家庭の就労状況、学校後の見守り困難、行動面の課題と療育目標等)を伝え、計画に反映してもらいましょう。
まとめ
– 放デイは、児童福祉法にもとづく「障害児通所支援」で、学校後や休業日に療育・生活支援を提供します。
– 利用料金は原則1割負担ですが、子どもの障害通所では月額の上限が「0円/4,600円/37,200円」の3区分(世帯の所得等で判定)。
同月内の利用は合算して上限管理されます。
おやつ・外出費などの実費は別途発生し得ます。
– 利用日数は自治体の支給決定(受給者証記載の支給量)で個別に定まり、送迎は事業所の体制と安全基準の範囲で提供されます。
送迎自体に追加の自己負担を求めないのが一般的です。
– 詳細は地域の運用(自治体要綱、事業所の重要事項説明)で異なります。
必ず自治体窓口と事業所で最新の説明文書を確認してください。
参考(根拠の所在)
– 児童福祉法(昭和22年法律第164号)および同施行令・施行規則
– 指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令・通知)
– 障害福祉サービス等の利用者負担に関する基準(厚生労働省令)、障害児通所支援の利用者負担上限月額に関する厚生労働省資料
– 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児通所支援)関係資料・通知
– 各市区町村の障害児通所支援実施要綱・利用案内
注 本回答は一般的な制度説明です。
金額・区分・運用は改正や自治体の方針で変わることがあります。
最新の正式情報はお住まいの自治体と利用予定の事業所でご確認ください。
良い事業所を選ぶには何を比較・確認し、見学時のチェックポイントは?
放課後等デイサービスとは(概要・対象・目的)
– 放課後等デイサービス(以下「放デイ」)は、学校に就学している障害のある子ども(おおむね6~18歳)を対象に、放課後や長期休暇中に通所して受ける「障害児通所支援」です。
法的には児童福祉法に位置づけられ、自治体の指定を受けた事業所が提供します。
– 目的は、単なる預かりではなく「自立支援と日常生活の充実」「社会性・学習・運動・コミュニケーションなどの発達支援」「保護者のレスパイト(休息)支援」等です。
厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」でも、個別支援計画に基づく計画的な療育の提供と家族支援、学校・関係機関との連携が重視されています。
– 提供内容の例 個別課題(認知・言語・学習支援)、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、感覚統合や運動プログラム、生活動作(ADL/IADL)練習、集団活動、地域交流、宿題支援、余暇支援、保護者面談・ペアトレ等。
医療的ケア児に対応する事業所では看護職員を配置してケアを実施します。
– 利用時間 授業日の放課後~夕方、学校休業日は日中の時間帯が一般的。
送迎を実施する事業所も多いです。
– 利用の流れ 相談支援事業所などで「サービス等利用計画」を作成→市区町村が支給決定(受給者証交付・支給量決定)→事業所と契約→アセスメント→個別支援計画作成→利用開始。
地域によりセルフプランが可能な場合もありますが、相談支援専門員による計画作成が推奨されています。
– 費用 原則1割負担(公費9割)。
世帯の所得に応じた「月額上限」があり、それを超えての自己負担はありません。
おやつ代・教材費・行事費・送迎費など実費が別途かかることがあります。
– 人員配置・資格(法令上の基準の概要) 管理者、児童発達支援管理責任者(児発管)を各1名配置。
児童指導員や保育士等を複数配置し、職員数は概ね「児童10人につき2人以上、以後10人ごとに1人以上」が目安(=最大でも15程度)です。
個別支援計画の作成・モニタリングは児発管が担い、少なくとも概ね6か月ごとに見直すことが求められます(ガイドライン・運営基準による)。
良い事業所を選ぶための比較・確認ポイント
1) 制度面・コンプライアンス
– 自治体の指定を受けた正式な事業所か(指定番号・開示情報の有無)
– 人員・設備・運営が「指定障害児通所支援の人員・設備・運営基準(厚生労働省令)」に適合しているか
– 自己評価(事業所向け・保護者向け)の実施と結果公表(ガイドラインで求められます)がなされているか
– 行政監査・指導の指摘事項、行政処分歴の有無(自治体の公開情報・事業所への直接確認)
– BCP(業務継続計画)、虐待防止の体制、個人情報保護・身体拘束等の適正化に関する方針・研修・記録が整備されているか
2) 支援の質と方法
– アセスメントが標準化され、強みとニーズに基づく目標が設定されているか(SMARTな目標、到達基準・評価方法の明確化)
– 個別支援計画が具体的で、保護者説明・同意・定期的モニタリングが行われているか
– エビデンスに基づく手法(例 TEACCH、ABA要素、SST、感覚統合の考え方、視覚支援、構造化、PBIS等)を、子どもの特性に合わせて柔軟に活用しているか
– 学校(担任・特別支援コーディネーター等)や医療(発達外来・療法士)との連携実績、サービス担当者会議の開催、連携記録の共有
– 保護者支援(面談・ペアトレ・家庭での一般化支援)、兄弟や家族全体への配慮
3) 人材・運営体制
– 児発管の経験年数・資格、児童指導員・保育士・言語聴覚士・作業療法士・公認心理師などの専門職配置状況
– 新任研修・継続研修・ケース検討会・スーパービジョンの仕組み、強度行動障害支援者研修の修了者配置
– 職員の定着(離職率や平均勤続年数)、人員の余裕(欠員時の代替体制)、1日あたりの利用人数と職員数のバランス
4) 安全・権利擁護
– 事故・ヒヤリハットの記録と再発防止策、緊急時対応(急変時の医療連絡・救急搬送手順)
– 送迎の安全管理(運転者の教育、車両点検、チャイルドシートや座席配置、送迎記録)
– 感染対策・衛生管理、災害時の避難計画・訓練
– 苦情受付窓口の明示、第三者による相談ルート(自治体・運営適正化委員会等)
5) 透明性・利便性
– 重要事項説明書・料金(実費・キャンセル料・振替規程)・加算算定の根拠と内容の丁寧な説明
– 連絡帳やアプリ等での情報共有、写真・SNS運用の同意とルール
– 立地・送迎範囲、開所日・時間、定員と待機状況、振替の柔軟性
– 特色(運動特化、学習特化、SST重視、感覚統合、アート・音楽等)とお子さんの目標との適合
見学時の実践的チェックポイント
– 子どもの様子
– 子どもがリラックスし主体的に活動しているか、成功体験が得られているか
– 年齢や発達段階に合う課題設定、困りごとが出た時の落ち着いた支援(予防的な環境調整、肯定的な声かけ)ができているか
– 過度な一斉指示や待機が長すぎないか、選択の機会が与えられているか、ピアとの関わりが促進されているか
– 職員の関わり
– 目線を合わせたコミュニケーション、短く分かりやすい指示、視覚支援の活用
– 記録の取り方(到達度・課題・次回への示唆)と、保護者へのフィードバックの質
– 新人とベテランの連携、声かけが一貫しているか(チームとしての支援)
– 環境・設備
– 見通しが持てる掲示(1日のスケジュール、ルール、視覚的手がかり)
– 刺激過多になりにくい工夫(騒音・照明・におい)、クールダウンスペース
– トイレ・手洗い・衛生環境、個人情報の掲示方法(氏名の丸見えになっていないか)
– 安全配慮(角の保護、施錠、避難経路、救急セット、アレルギー表示)
– プログラムと個別支援計画
– 個別支援計画やアセスメントの説明を求めた際に、根拠・方法・目標・評価が具体的に語られるか
– 家庭や学校での一般化支援の提案があるか(宿題支援のみで終わっていないか)
– 送迎・連絡体制
– 送迎時の引き継ぎ(出欠・体調・投薬等)の確認手順
– 連絡帳・アプリの記載内容(活動のねらいと評価まで書かれているか)
– 契約・情報提供
– 重要事項説明書の提示、実費の内訳、加算の算定理由と具体的な提供内容
– 自己評価表・保護者評価結果、第三者評価の実施状況、監査の指摘があれば改善内容
– 写真撮影・SNS投稿の同意と範囲、データの保管と削除ポリシー
– 雰囲気
– 見学者にも誠実に対応し、質問に対して透明性があるか
– 子どもの尊厳を守る言動(からかい・叱責・見せしめ的対応がないか)
よくある誤解と注意点
– 「学習塾のように宿題を見てくれる=良い」わけではありません。
ガイドラインは療育の質(個別性・発達支援・社会性の育成)を重視しています。
宿題支援は手段の一つであり、目的は子どもの発達・自立の促進です。
– 豪華な設備やイベントの多さが質を保証するわけではありません。
評価すべきはアセスメントと個別支援計画の質、職員の関わり、連携と安全管理です。
– 法人種別(株式会社・NPO・社会福祉法人等)より、管理と人材育成の仕組み、現場の実践が重要です。
– 子どもとの相性も大切です。
同じ「良い事業所」でも、お子さんの特性・目標に合うかは見学・体験で確認しましょう。
選定の進め方(実践手順の例)
1) お子さんの強み・課題・目標(半年~1年)を家族で整理
2) 相談支援専門員と地域の事業所情報を収集(自治体の指定情報・空き状況)
3) 候補を3~5か所程度に絞り、自己評価表・料金・特色を比較
4) 見学・無料体験を実施(上のチェックポイントを活用)
5) フィット感・通いやすさ・安全性・支援の具体性を家族で評価
6) 契約前に重要事項説明書と個別支援計画(案)を確認、疑問はすべて解消
根拠(法令・公的資料)
– 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
– 放課後等デイサービスは、同法に基づく「障害児通所支援」の一類型として位置づけられます。
市町村が支給決定(受給者証の発行、支給量)を行い、原則1割負担・所得に応じた月額上限が定められます。
– 指定障害児通所支援の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)
– 管理者・児童発達支援管理責任者の配置、児童指導員等の員数(児童10人に2人以上、以降10人ごとに1人以上の配置など)、記録整備、事故報告、虐待防止、苦情対応等の運営基準が定められています。
– 放課後等デイサービスガイドライン(厚生労働省)
– 個別支援計画の作成・モニタリング(概ね6か月ごと)、アセスメントの重視、学校・医療との連携、家族支援、自己評価(事業所用・保護者用)の実施と結果公表、質の可視化が求められています。
宿題支援等の単一目的化を避け、療育の質を高めることが示されています。
– 障害者虐待防止法および関連通知、運営基準の改正
– 虐待防止のための体制整備(責任者の設置、研修、指針、相談窓口)、身体拘束等の適正化、インシデント管理の強化が求められています。
– 災害対策・BCP関連の通知
– 障害福祉分野においても、感染症・自然災害等を想定した業務継続計画(BCP)の策定・訓練・見直しが段階的に求められています。
補足
– 各基準やガイドラインの最新内容は、厚生労働省およびお住まいの自治体の公式サイトで公開されています。
人員配置や報酬・加算、BCPや身体拘束等の取扱いは改正が入るため、最新情報をご確認ください。
– 迷ったときは、相談支援専門員、学校(特別支援コーディネーター)、地域の発達支援センター等に第三者的な視点で意見を求めると選定がしやすくなります。
以上を踏まえ、「制度に適合していること」「個別支援計画の質と連携」「人材と安全文化」「透明性と家族支援」の4点で比べると、納得度の高い選択につながります。
お子さんの目標と事業所の強みが合致するかを、見学・体験で丁寧に確かめてください。
【要約】
放課後等デイサービスは、就学児(概ね6~18歳未満)の障害児を対象に、放課後や休暇中に通所で発達・生活・社会性を支援する福祉サービス。手帳は必須でなく診断等で判断。個別支援計画に基づきSSTやADL/IADL、学習・就労準備を実施。自治体が支給決定し原則1割負担。利用は相談→計画→申請→受給者証→利用。
オーパコラム vol.2
オーパ利用についてはお気軽にお問合せください。