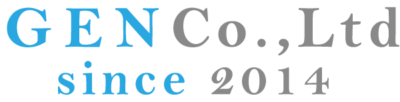個別支援計画は何のために作り、どんな価値を生むのか?
個別支援計画は、支援を「人」中心に設計し、合意した目標に向けて多職種・関係者が一貫した支援を行うための設計図です。
作成それ自体が目的ではなく、本人の生活の質(QOL)を高め、自立と参加を促し、支援の透明性と説明責任を担保し、成果を検証・改善するための基盤を作ることに真価があります。
以下、何のために作るのか、どんな価値を生むのか、そしてその根拠と、実際に何をどう考えて作るのかを詳しく整理します。
個別支援計画は何のために作るのか
– 本人の人生目標に沿った支援を可視化するため
支援者側の都合や制度枠ではなく、「本人がどう生きたいか」を起点に目標と手立てを言語化します。
本人の意思・希望・価値観を軸にし、強みや興味、環境資源も含めて全体像を見立てます。
– 支援を整合化し、再現性を高めるため
家族、福祉、医療、教育、就労など多関係者が関わる中で、役割分担、連絡体制、期日を明確にして、支援のばらつきや抜け漏れを防ぎます。
– 成果(アウトカム)志向の支援に転換するため
プロセス(やったこと)だけでなく、結果(できるようになったこと、感じ方の変化、参加の拡大)を測定し、計画→実行→評価→改善(PDCA)を回します。
– 権利擁護・意思決定支援の枠組みを保証するため
本人の同意、選択、合理的配慮の内容を記録し、必要な調整や代替的コミュニケーションの方法を明文化します。
虐待防止やリスクマネジメントとも連動します。
– 資源配分の妥当性と説明責任を担保するため
目標と手段の因果を示し、支援量・頻度・職種投入の妥当性を根拠づけます。
監査や評価への対応力も上がります。
個別支援計画が生む価値
– 本人にとっての価値
自己決定とエンパワメントが進み、自分の言葉で目標を語れる。
成功体験が積み重なり、参加範囲と社会的ネットワークが広がる。
生活満足度や安心感が高まる。
– 家族にとっての価値
役割や負担が見える化され、支援の見通しが持てる。
家族固有のニーズ(休息、情報、相談)も計画に組み込まれ、孤立を防ぐ。
– 支援者・組織にとっての価値
支援の質が標準化され、引き継ぎや新人教育がしやすくなる。
チーム内の認識がそろい、連携が円滑に。
成果が測れるため学習する組織文化が育つ。
– 地域・制度にとっての価値
断続的だった支援が切れ目なくつながり、医療・福祉・教育・就労・地域活動の資源が活用されやすくなる。
無駄や重複の少ない支援につながる。
作成の基本原則(何をどう考えるか)
– 本人中心(パーソンセンタード)
目標は本人の言葉で。
意思表明が難しい場合は意思決定支援を行い、過去の選好や行動、家族・キーパーソンの知見、ピアサポートを活用する。
– 強みベース
問題の列挙ではなく、強み・興味・成功体験・活用可能資源を起点に設計する。
– 生活全体の統合
住まい、健康、学び・仕事、余暇、対人関係、金銭・権利、移動・ITなど生活領域を横断して考える。
– SMARTな目標設定
具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限がある。
必要に応じてGAS(ゴール達成尺度)で段階目標を設定。
– 多職種協働と合意形成
役割・責任・連絡方法・意思決定のプロセスを明確にする。
本人・家族の合意を得て、変更時は説明と再同意を行う。
– リスクと自立のバランス
危険回避一辺倒ではなく、本人の挑戦と成長の機会を確保し、合理的なリスクテイクを支える。
– 継続的モニタリング
指標・頻度を決め、データとナラティブ(語り)で評価。
結果に基づいて計画を更新する。
– 権利擁護と倫理
プライバシー保護、最小制限、インフォームドコンセント、合理的配慮、虐待防止、差別の是正を明記する。
– アクセシビリティ
読みやすい言葉、ピクト・やさしい日本語、点字・音声・ICT等で本人が理解・参加できる形にする。
作成プロセス(標準的な流れ)
– アセスメント
生活歴、価値観、強み、ニーズ、健康状態、行動・コミュニケーション、環境資源、リスク、支援の効果・負担などを多面的に把握。
本人の語りを中心に、観察や標準化ツールも活用。
– 目標設定
長期ビジョン(1〜3年)と短期目標(1〜3カ月)を階層化。
本人にとって意味のある活動や参加の増加に焦点を置く。
– 支援戦略の設計
手立て、頻度、担当、連携先、合理的配慮、環境調整(物理・人的・制度)、テクノロジー活用、危機対応計画を具体化。
– 実施・記録
実施内容、反応、出来事、調整点を簡潔に記録。
データ(頻度、所要時間、独立度)と質的記述を併用。
– モニタリング・評価
進捗会議やカンファレンスでデータと本人・家族の実感を突き合わせ、ゴールの妥当性と手立ての効果を検証。
– 見直し・更新
継続・修正・中止を判断し、合意形成のうえで改訂。
ライフイベントや制度変更時は臨時見直し。
評価指標の例(アウトカムとプロセス)
– アウトカム例
参加機会の増加、対人ネットワークの拡大、自己決定の頻度、生活満足度、就労・学習の達成、健康・安全の維持、問題行動の機能的改善など。
– プロセス例
予定どおりの実施率、連携会議の開催、本人・家族の理解度、合理的配慮の実装、記録の質、苦情・ヒヤリハットの対応状況。
フィールド別の着眼点
– 障害福祉(成人・児童)
機能訓練偏重ではなく、日常生活と社会参加のアウトカムを重視。
意思決定支援と合理的配慮を計画に埋め込む。
児童では発達特性と家族支援の両輪で設計。
– 介護
自立支援・重度化防止、生活行為向上、認知症の非薬物的アプローチ、口腔・栄養・運動の統合、家族介護負担の軽減。
– 特別支援教育
個別の教育支援計画・指導計画として、教育目標と合理的配慮、学習・行動支援、学校と福祉・医療の連携、移行支援を明確化。
– 就労支援
職務分析、職場定着支援、ジョブコーチの関与、合理的配慮の交渉、通勤・時間管理・対人スキルなどの実践的支援。
よくある失敗と対策
– 形式化・コピペ化
対策 本人の語りと観察に基づくオリジナルのアセスメントを起点にする。
レビュー時に「本人の変化」を必ず検討。
– 支援メニューの羅列
対策 各手立てに明確な目的と評価指標を紐づける。
– 本人不在の会議
対策 参加方法を柔軟に(同席、事前ヒアリング、ビデオ・写真、ピクトボード)。
意思決定支援を実施。
– リスク回避の過剰
対策 可能性と安全の両立を議論し、段階的挑戦の枠組みを設計。
– 記録過少・データ不足
対策 最小限の重要指標を決めて簡便に継続測定。
データとナラティブをセットで残す。
根拠(法制度・ガイドライン・研究)
– 日本の法制度・通知等
障害者総合支援法および関連省令では、指定障害福祉サービス事業所に個別支援計画の作成・説明・同意・見直しが義務づけられています。
児童福祉法の枠組みでも、児童発達支援・放課後等デイサービス等における個別支援計画作成が指定基準に位置づけられ、厚生労働省の各ガイドライン(運営基準・評価票・自己点検表)で手順と質の確保が示されています。
介護保険法では居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が義務づけられ、本人同意・モニタリング・評価・更新が求められます。
特別支援教育では、文部科学省通知により「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成と関係機関連携が示されています。
さらに、厚生労働省の意思決定支援ガイドラインや虐待防止関連通知は、計画における同意・合理的配慮・最小制限の原則を根拠づけています。
– 実践ガイドライン
地域共生社会の実現をめざす各種指針、就労移行・定着支援、相談支援専門員の業務ガイドラインなどが、アセスメント→計画→実施→評価のPDCAと、多職種協働・本人中心支援の手順を具体化しています。
– 研究・エビデンス
パーソンセンタード・プランニング(PCP)に関する国内外の研究は、本人の選択機会やコミュニティ参加、生活満足、自然支援の活用が増えることを示唆しています。
知的・発達障害分野のレビューでは、PCPの導入により社会的ネットワークの拡大、日中活動の多様化、自己決定の増加が報告されています。
QOLの枠組み(Schalockらによる自決、社会参加、権利、ウェルビーイング等の領域)と整合的に、計画の質がアウトカムの改善と関連することが示されています。
また、GASを用いた目標達成評価は、個別目標の意味づけとエビデンスの統合を助けることが実証的に支持されています。
厳密な無作為化試験は限定的ですが、準実験や縦断研究、サービス評価研究において、PCPの導入群で満足度と参加の改善傾向が一貫して報告されています。
– 品質マネジメントの観点
医療・福祉の質管理(QI)文脈では、標準化された計画と指標化、モニタリングにより、ケアのばらつき削減、ヒヤリハットの低減、チーム意思決定の合理化が達成されることが報告されています。
これは個別支援計画のPDCA運用が安全性と効率性を高める根拠となります。
実践に役立つチェックリスト(抜粋)
– これは「誰の計画」かが冒頭で明確か(本人の言葉が反映されているか)
– 長期ビジョンと短期目標がつながっているか(SMART/GAS)
– 支援手立てに目的・頻度・担当・期限・評価指標があるか
– 合理的配慮と環境調整が具体化されているか
– リスクと挑戦の両方が検討されているか
– 連絡体制・役割分担・危機対応が明記されているか
– 本人・家族の同意、説明履歴、見直し予定日が記録されているか
– データ収集方法(何を、誰が、いつ)が定義されているか
– 本人が読める・理解できる形になっているか
まとめ
個別支援計画は、本人の人生に寄り添い、支援の質と成果を高めるための中核ツールです。
計画が生む価値は、本人のエンパワメントとQOLの向上、多職種協働の促進、説明責任と安全性の確保、資源配分の最適化、そして継続的改善の実現にあります。
法制度やガイドラインが義務づける背景には、こうした価値を社会全体で保証しようとする意図があります。
現場では、形式ではなく「本人の物語」と「測れる変化」を両輪に、強みベース・本人中心・PDCAという原則で運用することが、計画を生きた実践に変える鍵です。
本人理解とアセスメントは何をどう集めて読み解けばよいのか?
個別支援計画の質は、アセスメント(本人理解)で決まります。
つまり「何を」「どうやって」集め、「どう読み解くか」を体系化できれば、その後の目標設定・支援内容・評価がぶれにくくなります。
以下では、実務で使える視点と手順、具体的な収集項目、読み解きの枠組み、よくある落とし穴、そして根拠となるガイドラインや理論をまとめます。
前提に置くべき考え方(本人理解の原則)
– 本人中心・強みベース 困りごとより先に「大切にしていること」「得意・好き」「できていること」を把握します。
本人の価値観・希望を基点にしないと目標が“支援者都合”に傾きます。
– 参加(生活の文脈)に焦点 機能や行動単体でなく、生活場面・役割・社会参加での意味づけで捉えます(ICFの観点)。
– 双方向・継続的 アセスメントは一度きりで完了せず、仮説と検証を繰り返すプロセスです(PDSAサイクル)。
– 意思決定支援の組み込み 本人の意思表明の方法を確保し、選択肢を可視化。
推定意思・代弁の手順も準備します。
何を集めるか(領域別チェックリスト)
ICF(国際生活機能分類)に沿って、心身機能・活動・参加・環境・個人因子の5視点で抜け漏れを防ぎます。
生い立ちとライフストーリー
これまでの暮らし・転機・成功体験・喪失体験、価値観、アイデンティティ。
本人が「大切にしている日常」や「叶えたいこと」。
健康・医療
診断名・併存症・服薬・睡眠・てんかん発作の有無・疼痛・感覚特性(過敏/鈍麻)・栄養・嚥下。
認知・コミュニケーション
理解・記憶・注意・遂行機能の傾向、話し言葉/書字/AAC(写真・絵カード・デバイス等)、視覚支援の有効性、合理的配慮のポイント。
行動の特徴と機能
起こる場面・きっかけ・結果(ABC記録)、強化要因、疲労・過負荷・感覚刺激との関係、リスク(自傷・他害・逸脱・服薬中断)。
生活(ADL/IADL)
食事・排泄・入浴・更衣・整容、金銭管理、移動、家事、健康管理、時間管理、デジタル機器の扱い。
学習・就労・日中活動
興味・得意分野、集中できる条件、支援量と質、過去の適応/不適応の要因。
人間関係・家族
家族の価値観・期待、役割分担、ケア負担、意思疎通、支援ネットワーク(親族・友人・地域)。
住まいと地域生活
住環境のバリア・アクセシビリティ、移動手段、金銭・行政手続きの支援状況。
権利・意思決定
本人の意思表明の方法、同意能力の評価、代理同意のルール、合理的配慮の実施、虐待・権利侵害リスク。
目標とアウトカム
本人が語る短期・中長期目標、回避したいこと、成功の指標(本人の満足や達成感をどう測るか)。
どう集めるか(方法とコツ)
– 面接(半構造化・ナラティブ)
– 本人→家族→関係者の順に、重ねて聴きます。
本人の語りを最優先に据え、専門用語は避ける。
選択肢を視覚化したり、写真・実物を使うと効果的。
– 観察
– 複数の場面(静/動、得意/苦手、午前/午後、屋内/屋外)で、短時間×高頻度に。
ABC記録、スキャッタープロットでパターンを掴む。
– 標準化ツール
– 例 WHODAS 2.0(汎用的な生活機能)、Vineland-IIやABAS-II(日常生活スキル)、COPM(本人の重要課題の特定と評価)、感覚プロファイル、PBIS関連の機能的アセスメント。
施設・職種に応じて選択。
– 文書・データ
– 診療情報提供書、学校・職場の記録、過去の個別支援計画、モニタリング記録、事故・ヒヤリハット、服薬記録、睡眠・食事・排便記録。
– 多職種カンファレンス
– OT/PT/ST、看護、心理、医、相談支援、就労支援などでトリアンギュレーション(複数情報源の突合)。
仮説の一致/不一致を明確化。
– 倫理的配慮
– 同意取得と情報提供、本人に開示可能な言葉でのフィードバック、記録の最小限必要性、スティグマ化しない表現。
読み解き方(分析から計画への橋渡し)
– ICFマッピング
– 得られた情報を「心身機能」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」に整理。
例えば「通勤で遅れる」は、活動(時間管理)×参加(就労)×環境(交通・支援者)×心身(睡眠)に分解して課題と資源を特定。
– 強みとニーズの二軸で要約
– 強み(例 視覚情報の処理は速い)×ニーズ(例 口頭指示は取りこぼす)→視覚スケジュールの有効性という支援仮説に接続。
– ギャップ分析
– 本人の望む状態と現状の差を可視化。
ギャップに影響する修正可能因子(環境・支援・スキル)を抽出。
– 優先順位づけ
– 本人の重要度×安全リスク×実現可能性×資源の4指標でスコアリング。
短期(2〜3カ月)で手応えが得やすい領域から着手。
– 行動の機能分析
– ABCデータから、先行事象(要求過多、感覚過負荷)、行動(離席)、結果(要求回避が成立)を読み、代替スキル教授と環境調整、強化の設計(PBS)。
– SMART目標化
– 具体・測定可能・達成可能・関連性・期限付き。
例 「朝の通所準備を視覚スケジュールで自立度70%に、8週間で」。
– 指標設定
– アウトカム(参加・満足度・出席率)、プロセス(視覚スケジュールの提供率)、バランス(家族負担感)。
本人報告アウトカム(PRO)も取り入れる。
実装と見直し(PDSA)
– Plan 仮説に基づく支援内容、役割分担、環境調整、必要資源、リスク対策を具体化。
– Do 小さく試す。
例えば一日のうち午前のみ導入。
– Study 指標で効果検証。
本人の主観評価も聴く。
– Act うまくいった要素を拡大、合わない部分は修正。
新たな仮説を設定。
具体的に役立つ可視化ツール
– エコマップ 人的支援・関係性の強弱を見える化。
– ジェノグラム 家族構成と関係性の歴史的背景。
– 一日の流れ(ルーティン分析) 負荷が高い時間帯、切替の難所を特定。
– タイムライン 症状・出来事・支援介入の前後関係を整理。
よくある落とし穴と回避策
– 問題ベースのラベリング化 強み・関心・成功条件を必ず対で記載。
– 単一情報源への依存 本人・家族・現場・データの最低4点セットで確認。
– 本人の声の希薄化 語りにくい人には写真選択、スケール、実地体験を用意。
– 目標が支援メニュー化 サービス提供の有無ではなく、参加のアウトカムで書く。
– 過剰なスキルトレーニング偏重 環境・合理的配慮の先行実装を優先。
– 不変の計画 3カ月などの周期でモニタリングし、仮説を更新。
根拠(ガイドライン・理論・エビデンスの要点)
– ICF(国際生活機能分類, WHO 2001)
– 機能障害を個人要因に限定せず、活動・参加・環境因子を統合的に評価する枠組み。
日本の障害福祉でも活用が推奨され、個別支援計画の多面的アセスメントの根拠。
– 障害者の意思決定支援ガイドライン(厚生労働省, 2017 年公表・その後の通知で継続的に周知)
– 本人の意思を尊重し、情報提供・選択肢の提示・推定意思の活用・合理的配慮の実施などのプロセスを示す。
個別支援計画に本人の意向を反映させる根拠。
– 児童発達支援ガイドライン/放課後等デイサービスガイドライン(厚生労働省, 令和3年改訂)
– アセスメントと個別支援計画のPDCA、発達特性の理解、保護者・関係機関連携、可視化された目標設定を求める。
児童領域での標準実践の根拠。
– 介護保険のケアマネジメントプロセス(厚生労働省 介護支援専門員関連テキスト等)
– アセスメント→目標→計画→実施→モニタリング→再アセスメントの循環。
障害福祉でも共通するプロセスの根拠。
– WHODAS 2.0(WHO)
– ICFに基づく活動・参加の汎用評価ツール。
生活機能を標準化して把握する根拠。
– COPM(Canadian Occupational Performance Measure)
– 本人が重要と感じる活動を特定し、遂行度と満足度を測定する面接法。
本人中心・アウトカム志向の目標設定のエビデンス多数。
– Positive Behavior Support(PBS)/ 機能的アセスメント
– ABC記録や機能分析に基づき、問題行動の機能を同定し、環境調整と代替行動を設計する方法。
行動改善の効果に関する研究的根拠が確立。
– 日本の法制度の理念
– 障害者総合支援法、障害者基本法、障害者差別解消法は、本人の意思尊重・社会参加・合理的配慮を基盤にしており、個別支援計画の本人中心性と環境調整の根拠となる。
実務でのすすめ方(簡易フロー)
– 事前準備 既存資料の収集、仮説メモ作成、面接の質問票と視覚資料の準備。
– 初回面談 本人の価値観と望む生活の抽出、強みの把握、同意取得。
– 観察・追加面談・標準化評価 複数場面でデータを蓄積。
– 統合整理 ICFマッピング、強み/ニーズの要約、ギャップと優先順位決定。
– 計画化 SMART目標、支援内容、役割、リスク対策、評価指標を明記。
– フィードバック 本人にわかる言葉と形式(視覚化)で合意形成。
– 実施・モニタリング 短周期でのPDSA、小さな成功を記録・共有。
– 見直し 指標と本人の声に基づき再アセスメント。
最後に
「何をどう集めるか」はICFと本人中心の原則に基づき網羅的に、「どう読み解くか」は強みと環境をテコにして参加のアウトカムへつなげることが核心です。
データは仮説のために集め、仮説は本人の暮らしを良くするために使います。
これをチームで透明化し、本人に開かれたプロセスにできれば、個別支援計画は“書類”から“生活を変える道具”になります。
目標は本人の意思を尊重しつつどのように設定し、評価指標はどう決めるのか?
以下は、個別支援計画における「本人の意思を尊重した目標設定」と「評価指標の決め方」を、実務手順・尺度選び・合意形成・法的/学術的根拠まで含めて体系的にまとめたものです。
基本姿勢(何を大切に考えるか)
– 本人中心(パーソンセンタード)の原則 支援者や家族の都合ではなく、本人の価値観・希望・生活文脈を起点に組み立てる。
– 強み(ストレングス)基盤 困りごとだけでなく、できていること、興味、過去の成功体験を梃子にする。
– 参加(Participation)志向 機能や症状の改善だけではなく、地域生活・学業・就労・人間関係といった「人生の参加」を成果として重視する(ICFの視点)。
– 合意形成と意思決定支援 理解しやすい説明、視覚的ツール、擬似体験、選択肢の提示、代理意思の最小化などで「本人の決める力」を支える。
– 小さく試して回す(PDCA) 短期目標→やってみる→測る→見直すの反復で、現実適合と本人納得度を高める。
目標設定の手順(本人の意思を尊重しつつどう設定するか)
– アセスメントの多元化
– ナラティブ面接 本人の語り(何にワクワクするか、避けたいこと、将来像)を丁寧に聴く。
可能ならオープンダイアログ的な場を設ける。
– 生活歴・日課・環境 住まい、通学/通勤、移動手段、人間関係、役割。
阻害/促進要因(人・制度・物理環境)をICFの構造で整理。
– 観察とデータ 遅刻頻度、睡眠リズム、服薬遵守、感覚過敏のトリガーなど、日常の事実を集める。
– 周辺者の情報 家族・教師・雇用主の視点を「補助情報」として聴取。
ただし本人の意思を上書きしない。
– 意思決定支援の工夫
– わかりやすい資料(やさしい日本語、ピクト、写真)、ロールプレイ、体験見学、選択肢を2〜3に絞る、時間をおいた再面談などで選びやすくする。
– 代替的コミュニケーション(AAC、指差し、スケッチ、コミュニケーションブック)を活用。
– 目標の枠組み(SMART/SMARTER)
– 具体的(Specific)で、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、本人に意味(Relevant)があり、期限(Time-bound)を切る。
– 評価して見直す(Evaluate/Revise)まで含めると運用しやすい。
– 階層化
– 長期目標 半年〜1年で目指す「参加」や「役割」の姿(例 一般就労を目指す、地域サークルに参加)。
– 中期目標 長期目標に直結するスキル・環境調整(例 週3日通所の安定、通勤経路の獲得)。
– 短期目標 2〜8週で検証可能な具体行動(例 前夜23時就寝を週4日、朝の支度チェックリスト運用)。
– 共同記述
– 目標文は可能な限り「本人の言葉」で記す。
「私は〜したい/〜をやってみる」。
支援者の翻案が必要な場合、原文も併記する。
評価指標(何をどう測るか)
– 指標のタイプ(複合で設計する)
– アウトカム指標(結果) QOL、参加状況、就労日数、出席率、友人との交流回数、事故・入院減少など。
– プロセス指標(過程) 面談頻度、同行支援の実施率、支援記録の質、家族連携の実施など。
– 体験指標(PROMs/PREMs) 本人が評価する達成感、負担感、満足度、納得度。
– 安全指標 転倒・服薬ミス・逸走・ハラスメントの発生件数と重症度。
– 測定ツールの例
– GAS(Goal Attainment Scaling) 目標ごとに−2(開始時)〜+2(期待以上)の5段階を定義し、合意した「0(期待される達成)」を目安に評価。
個別性が高く、本人参加で作れる。
– COPM(カナダ作業遂行測定) 本人が重要な日常活動を挙げ、遂行度・満足度を10点尺度で測り変化を見る。
面接自体が本人中心。
– ICF/WHODAS 2.0 機能・活動・参加・環境要因を構造化して把握。
比較可能性が高い。
– 簡便な行動記録 週次の出席率、遅刻回数、セルフモニタリングシート等、現場で回るものを優先。
– 良い指標の条件
– 本人に意味がある、測り方が明確、現場で継続可能、短期変化を捉えられる、恣意性が小さい、リスク調整や個別事情を記述できる。
– 指標設計の実務
– ベースライン設定 直近2〜4週間の実績を数値化(例 起床できた日数、出勤日数)。
– 目標値・許容幅 例「4週後に週3日出勤(±1日を許容)」。
– 測定頻度・責任 誰が、いつ、どう記録するか(本人の自己記録を基本に、支援者が補助)。
– 可視化 カレンダー、トラッカーで見える化し、本人が進捗を実感できるようにする。
– 質的データの併記 数値だけでなく「何がうまくいったか/難しかったか」を短文で残す。
見直し(モニタリングとリビジョン)
– 定期レビュー 短期は2〜8週、中長期は3〜6カ月で見直し。
変化が早い時期はこまめに。
– 意味づけの再確認 目標が本人にとって依然として意味があるかを毎回確認。
意味が薄れていれば目標自体を変更。
– 介入の最適化 達成しないときは「本人のやる気不足」ではなく、環境調整不足・資源不足・支援方法のミスマッチを仮説検証。
– 小さな成功の強化 達成した時は何が奏功したかを特定し、次の目標に組み込む。
具体例(簡略)
– 例1 就労を目指すAさん(自閉スペクトラム)
– 長期目標 自分のペースを守りながら、飲食店の裏方で週3日働く。
– 短期目標 朝の出発準備をチェックリストで10分短縮(4週間)。
– 指標 準備に要する時間(分)、遅刻回数(週)、自己ストレス評価(0–10)。
GASで「0=平均20分で準備完了、遅刻週1回以下」等を合意。
– 支援 感覚過敏に配慮した制服素材の選定、職場見学2回、通勤ルートの実地練習。
– 例2 統合失調症のBさん(再入院を減らしたい)
– 長期目標 地域で安定して暮らし、週1回の趣味サークルに参加。
– 短期目標 服薬セルフマネジメントの確立(ピルボックスとアラーム活用)。
– 指標 服薬遵守率(週%)、早期警戒サインの自己記録件数、危機介入連絡のタイムラグ(時間)。
– 支援 WRAP(元気回復行動プラン)の共同作成、家族と危機対応合意書。
– 例3 児童発達支援Cくん(6歳)
– 長期目標 園での集団活動で安心して過ごせる。
– 短期目標 朝の切り替え時に視覚支援スケジュールを見て自分で次の場所に移動(週4日)。
– 指標 自発的移動の達成回数/週、支援者の声かけ回数、本人の表情・生理指標(必要に応じて)。
– 支援 視覚スケジュール、静かな待機場所の確保、先行手がかりの統一。
合意形成と倫理
– インフォームド・アグリーメント 目標・指標・測定方法・データの扱いを本人に明確に説明し同意を得る(本人が理解しやすい形で)。
– 本人のペース尊重 意思形成に時間が必要な場合は急がない。
短時間×複数回面談も有効。
– 代理意思の最小化 法定代理人や家族の意向は参考にしつつ、本人の推定意思と最善利益のバランスを取る。
記録に根拠を残す。
– 合理的配慮 環境調整・情報提供方法の工夫を通じて、本人が選択・参加できる条件を整える。
よくあるつまずきと回避策
– 抽象的すぎる目標 「社会性を高める」→「週2回、5分間の順番待ちを自力で達成」に具体化。
– 支援者主導の目標 施設稼働や家族都合を優先しない。
本人の大事さに直結する目標を優先。
– 測れない指標 主観のみ・他覚のみのどちらかに偏らせず、PROMsと観察の両方を使う。
– 過負荷 指標が多すぎると運用不能。
各期に3〜5本程度に絞り、残りは観察項目に。
根拠(法制度・ガイドライン・研究)
– 国際的根拠
– 国連障害者権利条約(CRPD) 自己決定の尊重(第12条)、地域生活への権利(第19条)、合理的配慮と参加の推進。
個人の意思と選好を中心に据えることを各国に要請。
– WHOのICF(国際生活機能分類) 心身機能だけでなく活動・参加・環境因子を包括的に捉える枠組み。
目標を「参加」に接続する根拠。
– 日本の制度・指針
– 障害者総合支援法・児童福祉法・介護保険法等 個別支援計画/居宅サービス計画/個別支援計画の作成と定期的見直し、本人意向の反映を義務づけ。
– 障害者基本法 個人の尊厳と自立、社会参加の促進を基本理念に掲げる。
– 厚生労働省の各サービス運営基準・ガイドライン(相談支援、就労系、児童発達支援・放課後等デイサービス等) 本人中心のアセスメント、個別支援計画のPDCA、モニタリング記録を明確化。
– 学術的根拠
– パーソンセンタード・プランニングやリカバリー志向支援が、満足度・QOL・地域参加・目標達成を改善することを示す国内外の研究が蓄積。
– GASの有効性 多様な障害領域・リハビリ・福祉で、個別目標の敏感な変化検出に有用とする報告が多数。
– 自己決定理論(Deci & Ryan) 自律性・有能感・関係性が動機づけと持続を高め、行動変容の定着に寄与。
– 動機づけ面接(MI) 本人の両価的感情に寄り添い、変化言語を引き出すことで自発的行動を促進。
実装のコツ
– 目標は「本人の物語」に置く 誰のための目標か、なぜ今それをやるかを一言で言えるかを確認。
– 指標は「測る前から決めておく」 ベースライン・目標値・測定責任・方法・レビュー時期を計画書に明記。
– 最小実行可能ステップ(Minimum Viable Step) 成功確率7割程度の小ステップに分解し、連勝体験を作る。
– 振り返りの喜びを共有 グラフ・カレンダー・スタンプなどで目に見える達成感を演出。
– 記録は短く、しかし要点を 数字+一言の質的メモで十分。
続く形に。
まとめ
– 目標は、本人の意思を中心に、参加をゴールに据えたSMARTな階層構造で共同設定する。
– 評価指標は、アウトカム・プロセス・体験・安全の複合で、ベースラインと測定計画を明確化し、GASやCOPM等を活用して「本人に意味のある変化」を捉える。
– この方法は、CRPD、ICF、国内の法制度と運営指針、そしてパーソンセンタード支援やGAS等に関する研究によって支持されている。
– 実務では、意思決定支援の工夫と小さな成功の積み重ね、定期的な見直しが鍵。
数字と物語の両方で進捗を確認し、本人とともに計画を育てていく。
支援の手立て・環境調整・多職種連携は具体的にどう設計し優先づけるのか?
個別支援計画は「本人の望む生活に近づくために、限られた資源で最大の効果を出す道筋」を可視化する設計図です。
支援の手立て・環境調整・多職種連携は、行き当たりばったりに並べるのではなく、本人中心の価値と科学的根拠に基づいて、緊急度と効果の大きさで優先づけし、チームで合意し、データで検証しながら更新することが肝要です。
以下に、具体的な設計手順と優先づけ、根拠を詳述します。
全体プロセスの見取り図
1) アセスメント(本人・家族の価値と強み、ニーズ、リスク、資源)
2) 目標設定(参加・生活の質に直結するSMART/GAS目標)
3) 優先づけ(安全・本人の重要度・波及効果・実現可能性・緊急性)
4) 支援の手立て設計(スキル獲得・補助・行動支援・ヘルスケア・テクノロジー)
5) 環境調整(物理・感覚・情報・社会制度・時間構造・合理的配慮)
6) 多職種連携の設計(役割分担、共有ゴール、情報連携、会議運営)
7) 実行・モニタリング(指標、頻度、担当、データ)
8) レビュー・更新(PDSAサイクル、合意形成、次の優先課題)
アセスメントの要点とツール
– 枠組み WHOのICFを基盤に、機能・活動・参加と環境因子を系統的に把握。
本人の価値・選好・強みを中心に据える(ストレングス・ベース)。
– 情報源 本人の語り、家族、観察、過去記録、学校・職場・医療情報、チェックリスト。
– ツール例
– 生活と参加 COPM、WHODAS2.0、GAS(後述)。
– 行動・自立 Vineland-3、ABAS、CBCL、機能的行動アセスメント(ABC記録、MAS)。
– 感覚・認知 Sensory Profile、MoCA等(専門職が実施)。
– 身体機能 FIM、転倒リスク評価、嚥下スクリーニングなど。
– リスク評価 生命・重大事故(誤嚥、転倒、逸走、自傷他害、服薬ミス)と権利侵害(自由の制限、虐待)を優先把握。
– 生活資源の棚卸し 家族・友人、自治体サービス、通所・就労、医療、福祉用具、ICT、金銭・移動手段、居住環境。
目標設定(本人中心・参加志向)
– 本人の望む生活から逆算して設定。
抽象目標を行動可能な短期目標へ分解。
– SMART原則(具体・測定可能・達成可能・関連性・期限)とGAS(Goal Attainment Scaling)で評価可能性を確保。
– 例 「週3回、近所のカフェで30分一人で過ごし、店員と挨拶を交わせる」を8週間で。
優先づけの原則と方法
– 優先基準(推奨の重み順)
1) 安全・重大リスク(生命・権利の保護)
2) 本人にとっての重要度(価値・満足度への直結)
3) 波及効果(他領域にも良い影響が広がる)
4) 実現可能性(資源・スキル・費用・時間)
5) 緊急性(タイミングの窓、学校・就労の期日)
6) 法令・制度要件(計画加算やガイドラインの必要項目)
– 実務テクニック
– スコアリング 各基準を1–5点で採点し重み付け合計。
上位から着手。
– MoSCoW Must(必須)/ Should(望ましい)/ Could(できれば)/ Won’t yet(今はしない)に分類。
– 限界設定 Mustは同時に3件以内。
過多は実行率と効果を下げる。
– 倫理的チェック その介入は本人の自己決定・尊厳・参加を増やすか?
負担や制限は最小か?
代替はあるか?
支援の手立ての設計(どう書き、どう実施するか)
– 方針 3本柱をバランスよく
1) スキル獲得(できることを増やす)
2) アコモデーション(やり方・道具で補う)
3) モチベーション・行動支援(望ましい行動が起こりやすい環境と強化)
– 構成要素
– 教授・学習 課題分析、連鎖化、プロンプトとフェイディング、差別強化(DRAなど)、トークン・エコノミー。
– コミュニケーション支援 AAC(絵カード、端末、スイッチ)、視覚的手がかり、社会的ストーリー。
– 日常生活 手順書、チェックリスト、タイムタイマー、動画モデリング。
– 健康管理 受診同行、服薬支援、栄養・睡眠・運動ルーチンの構築(医療職と連携)。
– 危機対応 トリガー回避、デエスカレーション手順、一次対応/連絡網。
– 文書化のコツ
– 行動レベルで具体化(誰が、いつ、どこで、何を、どのくらい、どうやって)。
– 頻度・所要時間・担当・必要物品・前提条件を書く。
– 成功基準(指標)と観察・記録方法を明記。
– 優先づけ
– まず「安全」「登校・就労継続」など生活の土台に直結する手立て。
– 次に「波及効果の大きいスキルトレーニング」(例 要求スキル、自己調整、移動)。
– 補助具やICTは即効性が高い場合が多く、早期導入→並行してスキル獲得が効率的。
環境調整(合理的配慮とユニバーサルデザイン)
– 物理環境 動線の単純化、危険物の除去、レイアウトのゾーニング、照明・音・温度の調整、転倒防止、視覚手がかりの明確化。
– 感覚環境 ノイズキャンセリング、感覚過負荷の回避、クールダウンスペース、触覚・前庭刺激の提供計画。
– 情報環境 視覚スケジュール、色分け、ピクト、簡潔な言語、リマインダー、手順書。
– 社会・制度環境 役割と期待の明確化、定常リズム、休憩・選択の権利、合理的配慮の合意文書化。
– 時間構造 予告、移行支援、タイムタイマー、ポモドーロ式など集中と休憩の周期。
– セキュリティ 出入口の管理、見守りレベル、個人情報や記録の保護。
– 優先づけ
– リスク低減の即効性が高い調整を先行(例 誤飲リスク→保管と手順を即日改善)。
– 変更コストが低く効果が広いものから(視覚スケジュール、騒音対策)。
– 人的環境(関わり方)の一貫化は最重要。
マニュアル化とトレーニングを早期に。
多職種連携の設計
– 体制と役割
– キーパーソン(サービス管理責任者/相談支援専門員/ケースマネジャー)が計画と全体調整を担う。
– 医療(主治医、看護、リハ)、教育(教師、コーディネーター)、福祉(支援員、PSW)、就労、家族がチーム。
– 共有ゴールとKPI
– 計画書の先頭に3つ以内の共有ゴールを明記し、各職種の寄与と指標を紐づけ。
– RACIで責任分担を明確化(Responsible/Accountable/Consulted/Informed)。
– 情報共有と会議運営
– 初回ケース会議でアセスメント統合→優先課題の合意→90日以内のレビュー頻度を設定。
– SBARで要点共有、SOAPで経過記録、インシデントは24–72時間以内に共有。
– 同意に基づく情報連携(個人情報保護/最小限必要の原則)。
– 連携の質を上げる工夫
– 共通用語はICF、共通フォーマットは単純に。
– 観察動画やデータダッシュボードで主観差を減らす。
– 想定シナリオ別のプロトコル(発作・パニック・転倒)を事前合意。
– 優先づけ
– リスク高・目標達成に必須の領域から関与を深める。
– 専門性が重複する場合は、誰が一次対応かを明確にして二重投薬・二重指導を避ける。
モニタリングと評価
– 指標設定
– アウトカム 参加頻度、GAS達成度、事故件数、QoL、本人満足。
– プロセス 実施率、遅刻・欠席、記録の充足率、家族/学校からのフィードバック。
– データ収集
– 短時間で継続可能な記録様式(チェックボックス、5段階評価、週次集計)。
– ABCや頻度データは特定課題期に集中的に。
– レビュー
– 月次ミニレビューと四半期のケース会議。
PDSAで仮説検証し、非効果的介入は速やかに中止・代替。
具体事例の優先づけ例
– 事例1 自閉スペクトラムの成人、通所でパニックと外出回避
– アセスメント 感覚過負荷(騒音)、予期不安、要求手段不足。
– 優先順位
1) 安全 パニック時の一次対応手順と避難スペース(Must)
2) 環境 騒音源のシールド、ノイズキャンセラ、視覚スケジュール(Must)
3) スキル 要求の機能的コミュニケーション訓練(DRA)(Should)
4) 活動 興味ベースの外出を段階的に(Could)
– 根拠 機能的行動評価とPBS、視覚支援の有効性。
– 事例2 高齢利用者、夜間転倒が複数回
– 優先順位
1) 物理環境 動線整備、照度、手すり、スリッパ交換(Must)
2) 健康 服薬・低血圧・夜間頻尿の医療連携(Must)
3) 行動 就寝前ルーチン、トイレ誘導、呼出手元化(Should)
4) 運動 日中の下肢トレーニングとバランス訓練(Should)
– 根拠 転倒予防は多要因介入が最も効果的というエビデンス。
– 事例3 発達障害の学生、提出物の遅延と不登校傾向
– 優先順位
1) 時間構造 課題を15分チャンク化、締切の見える化、週次チェックイン(Must)
2) 環境 静かな学習スペース、デジタルリマインダー(Should)
3) スキル 宿題の手順化、自己モニタリング、報酬設計(Should)
4) 連携 学校の合理的配慮(課題量調整、提出方法変更)(Must)
– 根拠 行動活性化と実行機能支援の研究、学校での合理的配慮の実務。
根拠(サマリー)
– ICF(国際生活機能分類) 機能・活動・参加と環境因子を統合的に捉える枠組み(WHO)。
– ポジティブ行動支援(PBS) 機能的アセスメントに基づく先行子介入・技能教授・強化・生活の質向上の多層介入は、知的・発達障害の行動課題の軽減に有効とする体系的レビューが蓄積。
– 先行子介入・視覚支援・機能的コミュニケーション訓練 自閉スペクトラムで中等度の効果が示される研究が多い。
– 転倒予防 多要因評価と多職種介入の組合せが転倒率を低下(Cochraneレビュー等)。
– 協働支援・ケースマネジメント 慢性期ケアや地域包括ケアでアウトカム改善のエビデンス。
– 法制度の根拠(日本)
– 障害者総合支援法・児童福祉法 個別支援計画の作成義務、支援の質向上のPDCA。
– 障害者差別解消法 合理的配慮の提供義務。
– 介護保険法 ケアプランと多職種連携。
– 障害者虐待防止法・個人情報保護法 権利擁護と情報共有の適正化。
– 各種ガイドライン(放課後等デイサービス、就労支援等)で本人中心・エビデンスに基づく実践が推奨。
使えるテンプレート(抜粋)
– プロフィールと強み・価値
– 生活目標(長期/短期/GAS)
– 優先度マトリクス(安全/重要度/波及/実現/緊急)
– 支援の手立て(目的→手段→手順→頻度→担当→指標)
– 環境調整(項目→具体策→導入日→責任者)
– リスク管理(危機サイン、対応、連絡網)
– 連携計画(チーム、役割、会議、共有方法)
– モニタリング(記録様式、週次・月次レビュー)
– 本人・家族の合意と同意
– 次回見直し日
よくある落とし穴と対策
– 介入過多で回らない→Must3件に絞る。
残りはバックログ化。
– 手段が目的化→「この介入はどの目標に紐づくか」を欄に明記。
– 人によって対応がバラバラ→関わり方マニュアルとOJT、観察チェックで整合。
– 本人の声が弱い→意思決定支援、ピクトや選択肢提示、代理同意の最小化。
– データを取らない→最小限の指標と記録フォーマットに統一。
– 連携が伝言ゲーム化→SBARと一枚要約、合意事項の議事録即日共有。
まとめ
– 優先づけの核は「安全」と「本人の大事にしていること」。
そこに「波及効果」と「実現可能性」のレンズを重ねる。
– 支援は「スキル獲得」「補助」「行動支援」をセットで設計し、環境調整で土台を固める。
– 多職種連携は、共有ゴール・役割の明確化・データ共有の仕組み化で「協働の質」を担保する。
– 計画は作って終わりではなく、データに基づくPDSAで磨き続ける。
この枠組みを用いれば、支援の手立て・環境調整・多職種連携を過不足なく設計し、限られたリソースでも最大の効果を狙うことができます。
必要であれば、実際のケースに合わせた優先度マトリクスや記録様式のひな型もお渡しできます。
実施後のモニタリング・評価・見直しはどの頻度・方法で回せば継続改善できるのか?
ご質問の「個別支援計画の実施後に、モニタリング・評価・見直しをどの頻度・方法で回せば継続改善できるか」について、現場で実装しやすい運用モデルと、その根拠を整理してお伝えします。
1) 前提と考え方(PDCA/PDSAで回す)
– 個別支援計画は「Plan(計画)-Do(実行)-Check(評価)-Act(改善)」の循環を意図した文書です。
継続改善には、大きいサイクル(3〜6カ月)と小さいサイクル(毎日〜毎週)を重ねて回す二層構造が効果的です。
– 目標はSMART(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)で設定し、事前に「何を・どの頻度で・誰が・どう測るか」を明記したモニタリング計画表を作ってから実行に移すと、評価・見直しがブレません。
2) 頻度の推奨(全体像)
– 毎日 個別支援記録(SOAP/PIEなど)と短い定点観察。
行動頻度、参加状況、リスクの気付きなどを簡潔に記録。
– 週1回 チーム・ミニレビュー(10〜15分のハドル)。
今週の達成・未達、次週の微修正、リスク共有。
必要に応じて小さなPDSAを設定。
– 月1回 ミニ評価会(30〜60分)。
KPIの集計(例 参加率、行動頻度、達成率、家族・本人の短い自己評価)、小目標の調整。
関係職種・必要に応じて家族からもコメント収集。
– 3カ月ごと 中間レビュー(ケース会議)。
半構造化面接、GAS(Goal Attainment Scaling)等の到達度評価、本人・家族の生活満足度や負担感聴取、支援仮説の検証。
必要なら支援強度や方法のテコ入れ。
– 6カ月ごと 正式な見直し(計画の更新)。
達成と課題の総括、新たな目標・支援内容・役割分担・モニタリング設計を更新。
合意形成と署名(本人・家族・関係者)。
– 年1回 総括レビュー。
年間の成果と学びを可視化し、次年度の重点と資源配分計画を定める。
– 臨時レビュー 重大インシデント、健康状態・家庭環境・就学就労環境の変化、目標の早期達成/停滞が起きた場合は、時期を待たず即時に再評価・対応変更。
3) 方法(測り方と場の持ち方)
– 指標設計(定量+定性の組み合わせ)
– 定量例 活動・参加の回数/時間、出席・定着率、作業生産性、ADL/IADL項目、コミュニケーション頻度、問題行動のABC記録(Antecedent-Behavior-Consequence)、自己記入式の達成スコア(0〜10)。
– 定性例 本人のナラティブ(何がうまくいったか/困っているか)、家族の体感、支援者の観察メモ。
– 尺度の例 GAS、WHODAS 2.0(生活機能)、Vineland系(発達・適応行動)、FIM/BI(介護領域)など、対象に適したものを選択。
– 記録様式と可視化
– 毎日の簡易記録+月次ダッシュボード(折れ線やRAG 赤黄緑)でトレンドを共有。
改善効果の有無を一目で判断。
– 会議運営
– 週次ハドルは短時間で事実共有と小さな意思決定。
月次はKPI確認と小目標調整。
3〜6カ月レビューは本人参加を原則とし、意思決定支援を行う。
– 意思決定ルール(例)
– 指標が2カ月連続で目標未達なら仮説を見直し、介入強度・方法・環境調整を変更。
– 目標が2回連続で達成・維持なら、目標を段階的に上げるか、他領域へ資源を再配分。
– 小さな実験(PDSA)
– 介入の「量・タイミング・手順・環境」を1〜2週間単位で試行し、データで是非を判断。
過度な一括変更を避ける。
4) 継続改善が回る実装ポイント
– 事前合意 頻度・指標・会議体・記録のルールを計画書に明記し、関係者の合意を取る。
– 権限と役割 サビ管/管理者が全体のPDCAを牽引、担当者は日々の測定・記録、相談支援/ケアマネは外部視点で妥当性をチェック。
– 負担最適化 測定項目は「最小で十分」を原則に、現場負担と情報価値のバランスを取る。
– 本人中心 本人の選好・価値に沿う目標設定と、理解しやすいフィードバック形式(絵・色・短い言葉など)を採用。
– 連携 学校・医療・就労先など他機関連携の情報も月次で反映し、齟齬を減らす。
5) 頻度設定の根拠(実務ガイドラインと品質改善の知見)
– 障害福祉・相談支援
– 厚生労働省の相談支援の業務ガイドライン等では、サービス等利用計画や個別支援計画は「定期的なモニタリングと概ね6カ月ごとの見直し」を基本として示されています。
状況変化時は随時見直しが必要とされています。
– 児童発達支援・放課後等デイサービス
– 児童発達支援ガイドライン/放課後等デイサービスガイドラインは、個別支援計画のPDCA運用を明示し、「毎日の記録・定期的なモニタリング・概ね6カ月ごとの評価と計画更新」を求めています。
短期目標を3カ月程度で点検する実践も広く推奨されています。
– 介護保険領域(ケアマネジメント)
– 介護支援専門員の実務テキスト・自治体運用では、少なくとも月1回のモニタリング(状態変化時は随時)と、3〜6カ月を目安とした計画の再評価が標準的実務として位置づけられています。
– 医療・福祉の品質改善(QI)
– PDSA(Plan-Do-Study-Act)サイクルはIHI等の国際的枠組みで、2〜8週間程度の短サイクル検証を重ねることが効果的とされています。
個別支援でも「週次ハドル+月次データレビュー+四半期/半期レビュー」の多層サイクルはQIの理論と整合します。
6) 実装テンプレ(例)
– モニタリング計画表
– 指標A 午前活動への参加率(%)/担当 〇〇/頻度 毎日→月次集計/方法 チェックリスト/目標 4週平均80%以上
– 指標B 不安行動の頻度(回/日)/担当 △△/頻度 毎日ABC記録→週次件数化/目標 3カ月で50%減
– 指標C 本人満足度(0〜10)/担当 支援者/頻度 月1回面接/目標 平均7以上
– 会議体
– 週次10分 達成/課題/翌週PDSA
– 月次45分 ダッシュボード確認、短期目標修正
– 3カ月 ケース会議(本人・家族参加)
– 6カ月 計画更新・同意
– 意思決定基準
– 2カ月連続未達→介入再設計、必要に応じて外部助言
– 目標達成継続→段階的難易度アップまたは他領域へシフト
7) 注意点
– 過剰測定の回避 測るほど良いわけではありません。
意思決定に使わない指標は削減し、現場の余力を支援そのものに振り向けます。
– リスク管理 急性の健康リスク・虐待兆候・重大インシデントは通常サイクル外で即時対応・報告・原因分析(ヒヤリハット含む)。
– 倫理・権利擁護 本人の意思決定を支援し、同意を得た範囲で情報共有。
個人情報の適切な管理は必須。
8) 小さなケース例(簡略)
– 目標 朝の集団活動への参加率を3カ月で50%→80%へ
– 介入 開始15分前の視覚予告+ピアサポート配置+活動後の選択強化子
– 計測 毎日参加有無、離席回数、本人の負担感スコア(0〜10)
– 運用 週次ハドルで予告のタイミングをPDSA、月次で参加率と負担感を確認、2カ月目に強化子を調整、3カ月レビューで達成を確認し次の目標(活動内の発言回数)へ移行
まとめ
– 継続改善を実現する頻度の目安は「日々の記録+週次ハドル+月次ミニ評価+3カ月中間+6カ月正式見直し+臨時レビュー」。
これを、本人中心の指標設計と小さなPDSAで支えるのが実装のコツです。
– 根拠は、厚生労働省系ガイドラインにおける「定期モニタリングと概ね6カ月ごとの見直し」の要請、および医療・福祉の品質改善分野で確立したPDSAの短サイクル実践にあります。
– 重要なのは、頻度それ自体よりも「事前合意された測り方」「小さく早く試してデータで決める」「本人とともに評価する」の3点を外さないことです。
これにより、過度な負担なく、確実に成果へ近づくサイクルが回ります。
【要約】
個別支援計画は、本人の意思と強みを起点にQOL向上と自立・参加を実現する設計図。多職種で役割を明確化し、成果指標でPDCAを回す。権利擁護と合理的配慮、リスクと自立の両立を明記。アセスメント→目標設定(SMART)→支援設計(頻度・担当・環境調整)→実施・モニタリングで継続改善。本人・家族・組織・地域に価値を生む。透明性と説明責任を担保し、引き継ぎや連携の再現性を高める。アクセシビリティや倫理にも配慮。
オーパコラム vol.7
オーパの利用についてはお気軽にお問合せください☆