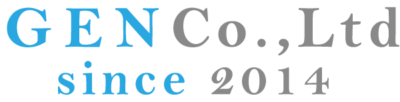障害児相談支援事業所とはどんな役割で、具体的に何ができるのか?
障害児相談支援事業所は、障害のある子どもとその家族が必要な福祉・医療・教育等の支援を切れ目なく受けられるよう、相談受付からアセスメント、計画作成、サービス調整、見直しまでを一貫して伴走する「地域のハブ(総合調整役)」です。
いわば、個別の状況に合わせた「支援の道筋(ルート)」を一緒に描き、関係機関と連携して実行をサポートする役割を担います。
利用者負担は原則ありません(相談や計画作成・調整は公費で賄われます)。
何ができるのか(主な業務)
– 初回相談・情報提供
– 子どもの発達や行動、就園・就学、医療的ケア、きょうだい支援、家族の負担、経済面など幅広い相談に応じ、利用可能な制度・サービスを案内します。
– 例 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、短期入所(ショートステイ)、日中一時支援、地域の親子教室・発達支援プログラム、自立支援医療(育成医療)、補装具、各種手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)など。
アセスメント(課題・強みの整理)
厚生労働省の標準様式を用いつつ、生活全体を見渡して課題と強み、家族の状況、環境要因を多面的に把握します。
必要に応じて自宅・園・学校・医療機関等を訪問し、実態を確認します。
障害児支援利用計画の作成
家族と合意形成しながら、「目標(例 朝の身支度の自立、集団場面での不安軽減)」「支援方針」「役割分担」「利用するサービスの組み合わせ・頻度」「危機対応(緊急連絡体制)」などを明確化した計画書を作成します。
子どもの意思・興味・得意を軸に据え、過度な負担や過密スケジュールにならないよう調整します。
受給者証の申請支援・行政手続きの伴走
市町村への支給申請書類の整備、必要書類の案内(医師意見書等)、申請手順の説明・同行等を行います。
給付決定(受給者証交付)後の各種変更・更新手続きもサポートします。
セルフプラン(家族が自ら計画を作る)とするか、事業所作成とするかの選択を案内します。
事業所選定・調整・サービス担当者会議
地域の事業所の特性・空き状況・送迎・専門性を踏まえ、複数候補を提示し、見学・体験の段取りを支援します。
園・学校・医療・療育・福祉が一堂に会する会議(サービス担当者会議等)を開催・司会し、目標と役割を共有します。
医療的ケア児については訪問看護・在宅医・学校との連絡体制を整えます。
モニタリング・計画見直し
少なくとも6か月ごと、必要に応じて随時、利用状況・目標達成度・家族の負担感を確認し、計画を見直します。
事業所の個別支援計画(児童発達支援管理責任者が作成)との整合性をチェックします。
権利擁護・虐待防止・危機対応
人権・プライバシーの保護、合理的配慮の実現を支援します。
虐待が疑われる場合の通告・関係機関連携、いじめ・不登校・医療中断・家族のメンタル不調などの緊急時対応計画を作ります。
ライフステージの移行支援
就園・就学・進学・卒業・18歳到達(成人期サービスへの移行)など節目の準備を支援します。
高校卒業や18歳前後には、成人向けの特定相談支援(サービス等利用計画)へのスムーズな引継ぎをコーディネートします。
家族全体への支援
介護負担の軽減(短期入所・レスパイト)、きょうだい支援、ペアトレや家族会の紹介、経済的支援制度の案内、在宅サービスとの両立支援、就労両立の相談など。
苦情・意見の受付と調整
事業所間の調整、支援内容の見直し、納得のいく説明・再検討の場の設定などを行います。
利用の流れ(標準的なケース)
– 相談申込(電話・窓口・紹介)→初回面談・説明
– アセスメント(必要に応じ訪問・関係機関からの情報収集)
– 計画(案)作成・同意
– 市町村へ支給申請(受給者証)手続きの伴走
– 事業所見学・マッチング→サービス担当者会議→利用開始
– モニタリング(6か月程度ごと)→計画見直し
できること・できないことの境界
– 相談支援はコーディネートと計画づくりが中心で、療育・訓練そのものは実施しません(それは通所事業所の役割)。
– 医学的診断は行いません(医師の所管)。
就学先の決定権も持ちません(教育委員会・学校との協議を支援します)。
– サービス量の最終決定は市町村(支給決定権者)が行います。
相談支援は必要性を整理し提案・根拠提示を担います。
費用
– 相談・計画作成・調整は原則無料です(給付費は公費)。
通所・在宅等の実際のサービス利用には原則1割負担が生じますが、所得に応じた月額上限があります。
事業所選びのポイント
– 医療的ケア児や強度行動障害など、求める領域の対応実績
– 学校・医療との連携経験、会議の運営力
– 訪問・面談の頻度、緊急時の連絡体制、オンライン対応
– 相談支援専門員の資格・経験、主任相談支援専門員の配置
– 説明の分かりやすさ、記録や同意の丁寧さ
根拠(法令・通知・基準)
– 児童福祉法
– 障害のある児童に対する通所支援や相談支援の枠組みを規定。
市町村が支給決定を行い、相談支援事業所が「障害児支援利用計画」を作成してサービスの総合調整を行うことが定められています。
– 児童福祉法施行規則
– 申請・支給・計画等の手続や様式に関する詳細を規定。
– 厚生労働省令「指定障害児相談支援の人員、設備及び運営に関する基準」
– 相談支援専門員の配置、資格要件、運営基準(アセスメント・計画作成・サービス担当者会議・モニタリング・記録・個人情報保護・苦情解決など)を具体化。
– 厚生労働省通知・ガイドライン
– 障害児相談支援ガイドライン
– 記録・アセスメント様式、モニタリング周期、教育・医療との連携、虐待対応、医療的ケア児支援体制等に関する留意事項を提示。
– 障害者総合支援法
– 18歳以降の「特定相談支援(サービス等利用計画)」の仕組みや、相談支援専門員の研修体系・事業運営の基本を規定。
児童期から成人期への移行連携の根拠ともなります。
– 関連制度
– 自立支援医療(育成医療)制度、補装具費支給制度、特別児童扶養手当・障害児福祉手当、障害者虐待防止法(通報・対応)など。
相談支援はこれらの活用を案内・調整します。
実務上のポイントとよくある支援例
– 幼児期 発達の遅れが気になる→発達検査・医療受診の同行調整→児童発達支援+保育所等訪問支援を組み合わせ、家庭ではペアトレ紹介→短期入所でレスパイト導入。
– 学齢期 学校での不安・行動課題→学校と役割共有の会議開催→放課後等デイの選定と個別目標の連携→福祉と学校が同じ目標(例 授業参加時間を延ばす)で働きかけ。
– 医療的ケア児 在宅医・訪問看護・学校・通所の多機関連携→緊急時対応表・連絡網整備→吸引・経管栄養等の手順共有。
– 思春期~卒後 進路選択と職業準備→体験実習やジョブコーチにつなぐ→18歳時に成人の特定相談支援へ引継ぎ会議。
個人情報・同意・権利
– 情報共有は原則として保護者(必要に応じ本人)の同意に基づきます。
虐待等の緊急時は法令に則り通報・保護を優先します。
– 本人の意思決定支援(わかりやすい説明、選択肢の提示、ペース配慮)を重視します。
どこに相談すればよいか
– お住まいの市区町村の福祉窓口(障害福祉課・子育て支援課等)に「障害児相談支援事業所の一覧」を問い合わせる
– 都道府県や市区町村のウェブサイト「福祉のしおり」「障害児支援」ページで検索
– 医療機関・学校・地域包括(子ども家庭総合支援拠点)からの紹介
最後に
障害児相談支援事業所は、サービスの「窓口」ではなく、家庭と地域全体をつなぐ伴走者です。
制度や事業所の事情は地域により差があるため、まずは現状や希望を率直に伝えてください。
計画は固定ではなく、子どもの成長や家族の状況に合わせて柔軟に見直せます。
根拠法令に基づく公的な仕組みですから、遠慮せずに活用し、必要な支援にたどり着くためのパートナーとして役立ててください。
誰が利用できて、利用することでどんなメリットがあるのか?
ご質問の「障害児相談支援事業所でできること」「誰が利用でき、どんなメリットがあるか」「制度的な根拠」について、できる限り平易に、ただし実務の流れがイメージできる程度に詳しくお伝えします。
障害児相談支援事業所とは
障害児相談支援事業所は、発達や行動、身体機能、医療的ケアなどに配慮が必要な子どもとその家族の相談に応じ、必要な支援を組み立てる「計画相談(ケアマネジメント)」を担う専門機関です。
所属する相談支援専門員が、課題の聞き取りとアセスメント、サービス等利用計画の作成、関係機関との調整、利用後のモニタリングまでを一貫して行います。
イメージとしては、子どもと家族の「伴走者」「コーディネーター」です。
誰が利用できるか(対象者)
以下に該当する方が対象です。
診断名や障害者手帳の有無は必須条件ではなく、心配事や困りごとがある時点で相談できます。
年齢
0歳からおおむね18歳までの子ども。
高校在学中は18歳を超えていても対象になり得ます。
成人期への移行準備(18歳前後)も相談可です。
障害の種別
知的障害、肢体不自由、視聴覚障害、発達障害(ASD、ADHD、LDなど)、精神障害、難病、医療的ケア児(たん吸引、経管栄養等を伴う)など、幅広いケースが対象です。
診断・手帳の要否
診断が未確定でも相談可能です。
障害者手帳も必須ではありません。
サービスの種類によっては「受給者証」(市町村が発行)が必要ですが、その取得の手続き自体を相談支援事業所が支援します。
利用主体
子ども本人、保護者・家族、学校や医療機関からの相談も受け付けます。
家族がまず相談し、必要に応じて本人と面談する流れも一般的です。
居住要件
原則、住民票のある市区町村が所管です。
その市区町村が指定した「障害児相談支援事業所」を自由に選べます(近隣市の事業所を選べるかは自治体運用によります)。
相談支援事業所でできること(主な機能と具体的内容)
相談支援の中核は、初期の計画づくりと、その後の継続的な見直しです。
具体的には次のような支援が受けられます。
初回相談・アセスメント
困りごとの整理、強みや興味の把握、家庭状況、就園・就学状況、医療的配慮、行動特性などを丁寧に聴き取り、生活全体の像を共に描きます。
必要に応じて学校・園・医療機関とも情報共有(同意のもと)を行います。
サービス等利用計画の作成
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援、短期入所(ショートステイ)、日中一時支援(自治体事業)などの必要性と優先度を整理し、利用目標・頻度・連携体制を計画書として可視化します。
保護者の休息(レスパイト)やきょうだい支援、送迎の必要性なども検討します。
受給者証の取得支援
市区町村への支給申請の準備(必要書類の案内、医師意見書の手配、申請書作成の支援、場合により委任による提出)や、判定・面接への同行、支給決定後の手続きフォローまで支援します。
事業所選び・調整
各サービス事業所の特徴や空き状況を踏まえた紹介・見学調整、複数事業所の併用調整、送迎や利用時間の調整、個別支援計画とのすり合わせなどを行います。
医療的ケア児の場合は訪問看護、学校との医療連携も含めて調整します。
モニタリング(定期的な見直し)
概ね6か月に一度(必要に応じて随時)、利用状況や目標の達成度、副作用的な負担の有無、環境の変化(学年進行、転居、家族の就労変化など)を確認し、計画を見直します。
事業所との合同会議を持つこともあります。
教育・医療・福祉の三者連携
就園・就学先(保育所、こども園、学校)、医療機関(小児科、発達外来、リハビリ)、保健センター、児童相談所、子ども家庭支援センター、自治体の子育て支援窓口など、多機関連携のハブとして機能します。
制度横断の情報提供・権利擁護
利用者負担の仕組み(負担上限月額)、障害児通所給付、地域生活支援事業、医療保険・自立支援医療(精神通院・育成医療)との併用、就学支援(特別支援教育、合理的配慮、通学支援)、福祉用具・補装具、手当(特別児童扶養手当 等)、災害時配慮などの情報提供や申請支援を行います。
困難事案では苦情・権利擁護の仕組みや第三者機関の活用も案内します。
ライフステージ移行支援
就学前から小学校、中学校、高校、卒業後の成人福祉(就労移行・継続支援、地域生活)への「切れ目のない」移行を見据え、早めに準備を始めます。
18歳前後は成人の特定相談支援への引継ぎを調整します。
緊急・一時的支援のコーディネート
家庭の急な事情による緊急保護・ショートステイ、学校での著しい不適応や医療的急変への対応資源の案内など、危機時の選択肢を一緒に準備・確保します。
家族支援・ピアサポートの紹介
ペアレントトレーニング、保護者会、家族会、きょうだい会、相談できるコミュニティの紹介など、家族の孤立を防ぐ支援にもつなげます。
3-1. 費用について
– 障害児相談支援(計画相談)は、原則として利用者負担はありません。
事業所は公費により報酬請求します。
面談に伴う交通費等の実費が発生する場合は事前説明があります。
– 相談の結果、個別の通所支援等を利用する際は、世帯の所得に応じた「月額の負担上限」が設定されます。
詳細の金額区分は自治体の最新案内で確認します。
利用するメリット
– 必要な支援の全体像を整理できる
困りごとが多岐にわたるほど、どれから手を付ければよいか迷いがちです。
相談支援では優先順位を据え、短期・中期の目標に落とし込み、無理のない利用頻度と連携体制を計画化します。
結果として、家族が迷いにくくなり、子どもの負担も過剰になりにくくなります。
– 受給者証取得と行政手続きがスムーズ
必要書類や医師意見書の手配、申請の段取り、窓口との調整まで伴走するため、手続きの抜け漏れや待機の長期化を防ぎやすくなります。
– サービスのミスマッチを減らせる
発達特性や医療的ニーズに合った事業所選び、通所と在宅支援のバランス調整、送迎の現実性の確認などにより、「通ってみたが合わなかった」「家族の負担が増えた」という事態を減らします。
– 事業所間・学校との連携が進む
計画書をベースに、事業所の個別支援計画や学校の個別の教育支援計画と目標の整合を図ることで、家庭・教育・福祉の方向性が揃い、子どもに一貫した支援が届きやすくなります。
– 利用後も定期的に見直せる
成長や環境変化に応じて支援ニーズは変わります。
モニタリングにより、合っていない支援を早めに調整でき、過不足を最小化できます。
– 家族の負担軽減と安心感
レスパイトの計画的利用、送迎等の調整、制度の横断活用により、介護・育児負担や経済的負担の軽減が図れます。
困りごとの早期相談先が明確になること自体が安心につながります。
– 権利擁護・トラブル時の調整役
事業所との契約・運用で困った際、第三者として相談支援専門員が調整役となり、必要に応じて自治体や苦情解決機関へのつなぎも行います。
– 成人期へのスムーズな橋渡し
高校進学・卒業、就労準備、成人サービスへの切替えなどの節目に、必要なタイミングで情報提供と手続きを前倒しで進められます。
利用の流れ(典型例)
– 相談申込み お住まいの市区町村(障害福祉・こども家庭・発達支援担当)や、近隣の障害児相談支援事業所へ直接連絡。
– 初回面談・同意 困りごと・希望を確認。
個人情報の同意書を取り交わします。
– アセスメント 家庭・園校・医療等から必要な情報を収集。
必要に応じて見学・同行。
– 計画作成 サービスの目標・内容・頻度・連携体制を明記した「サービス等利用計画」を作成し、ご家庭と合意。
– 受給者証申請 市区町村へ支給申請。
審査・判定を経て受給者証が交付。
– 利用開始・調整 各事業所と契約・利用開始。
運用中の課題は相談支援専門員が調整。
– モニタリング 概ね6か月ごとに評価・見直し。
必要時は随時変更。
よくある誤解の整理
– 「診断が出るまで相談できない」→誤り。
診断前でも相談可能で、医療受診の段取りも含めて支援します。
– 「相談支援は施設を紹介するだけ」→不十分。
計画作成、関係機関連携、モニタリングまで含むケアマネジメントが本体です。
– 「一度決めた計画は変えられない」→誤り。
状況変化に応じていつでも見直し可能です。
– 「自己負担が高い」→相談支援自体は原則無料。
個別サービスは世帯所得に応じた月額上限が設定されています。
制度と法的根拠(概要)
– 児童福祉法
障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援など)や障害児相談支援の枠組み、支給決定(受給者証)と負担上限の仕組みを定めています。
障害児相談支援は、市町村が指定する「指定障害児相談支援事業者」による計画相談として位置づけられています。
– 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(いわゆる障害者総合支援法)
相談支援(特定相談支援)に関する基本的な考え方や、ケアマネジメント、モニタリング、地域資源の活用、権利擁護などの理念・手続の大枠を規定し、成人期のサービス体系と接続しています。
18歳前後の移行支援は本法体系との接続で行います。
– 厚生労働省の通知・ガイドライン
厚生労働省は「計画相談支援(障害児相談支援)ガイドライン」「相談支援専門員の業務指針」「障害福祉サービス等の概要」等で、アセスメント様式、モニタリング周期、セルフプランの扱い、サービス等利用計画の必須化の方向性、他機関連携の方法などを具体化しています。
近年の報酬改定通知でも、障害児通所支援の利用には原則として「サービス等利用計画」の作成・活用が求められることが繰り返し示されています。
– 自治体の実施要綱・運営基準
市区町村は、指定・監査・報酬請求の実務、受給者証の判定基準、負担上限の運用、セルフプラン可否の方針、地域生活支援事業(例 日中一時支援)の位置づけ等を定めています。
具体の運用は自治体により差があるため、最新のローカルルールは必ず所管課で確認します。
事業所を選ぶ際のポイント
– 得意分野 発達障害、医療的ケア児、重症心身障害など、強みのある分野が事業所により異なります。
– 連携力 学校・医療・福祉との会議を丁寧に開いてくれるか、報告・共有の質はどうか。
– アクセス・面談方法 訪問対応の可否、オンライン面談の有無、緊急時の連絡体制。
– 相性 家族の価値観や語りやすさも大切です。
変更や乗り換えも可能です。
小さな注意点
– 相談支援の利用は原則無料ですが、個別サービス利用には上限付き自己負担が発生します。
特に多サービス併用時は家計見通しを相談支援専門員と共有すると安心です。
– 自治体によりセルフプラン(家族が自ら計画作成)の扱いは異なり、原則は専門員作成です。
事情により例外扱いがあるかは所管課に確認してください。
– 学校との情報共有や医療情報のやり取りは必ず同意のもとで行われます。
開示範囲は事前に確認しましょう。
まとめ
障害児相談支援事業所は、子どもと家族の困りごとを全体として整理し、必要な支援をつなぎ、定期的に見直す「伴走型のコーディネーター」です。
診断や手帳がなくても相談でき、受給者証の取得から事業所選び、学校・医療との連携、家族のレスパイト確保まで、一連のプロセスを専門的に支えます。
相談自体は原則無料で、制度や地域資源を横断的に使いこなすことで、子どもの成長と家族の暮らしが持続可能になるという大きなメリットがあります。
根拠は児童福祉法および厚生労働省のガイドライン・通知群に基づく制度設計で、自治体の実施要綱により具体運用が定められています。
まずはお住まいの市区町村の障害福祉・子ども家庭担当か、お近くの指定障害児相談支援事業所に連絡し、初回相談の予約から始めてみてください。
参考になる公的情報(名称)
– 厚生労働省「障害福祉サービス等の概要」
– 厚生労働省「計画相談支援(障害児相談支援)ガイドライン」
– 児童福祉法(障害児通所支援・障害児相談支援に関する規定)
– 障害者総合支援法(相談支援の基本枠組み、成人期への移行に関する規定)
– 各市区町村の「障害児通所給付・受給者証のご案内」「障害児相談支援の手引き」
ご事情に応じて、もう少し具体的な流れ(例 発達障害が疑われる未就学児、医療的ケア児、学校不適応が強い中学生など)にも落とし込めます。
必要でしたらケースに合わせて個別に整理します。
サービス等利用計画はどのように作成され、どんなサポートが受けられるのか?
ご質問の「障害児相談支援事業所でできること」と「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成方法・受けられる支援」について、実務の流れと法的根拠も含めて詳しく説明します。
なお、児童分野では正式名称は「障害児支援利用計画」ですが、自治体や現場では「(障害児の)サービス等利用計画」と呼ばれることも多いため、以下では両者を同義として扱います。
位置づけと基本
– 障害児相談支援事業所は、保護者・お子さんの相談を受け、本人中心のケアマネジメントを行い、障害児通所支援等の利用につなぐ拠点です。
– 児童福祉法に基づく「支給決定(受給者証の発行)」と一体で運用され、計画は支援の中核になります。
– 対象となる主なサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、短期入所(日中一時含む地域生活支援事業)、必要に応じ障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護など)や移動支援等です。
計画(障害児支援利用計画)の作成プロセス
概ね次のステップで進みます。
自治体や事業所により手順名や順番の呼称が多少異なることがあります。
相談受付・初回面接
家庭状況、困りごと、通園・通学の様子、医療や療育歴、家族の希望(将来像)を聴取します。
緊急性(学校での不適応、家族の介護負担、医療的ケアの課題など)があれば優先調整します。
アセスメント
相談支援専門員が、お子さんの発達特性、健康・医療ニーズ、日常生活能力、行動上の課題、感覚特性、コミュニケーション、家庭資源、学校・保育園の支援体制、地域資源などをICFの視点も踏まえて体系的に評価します。
必要に応じて医療機関の意見、学校・園の見解も聴き取ります。
計画案の作成
長期目標(1年程度)と短期目標(3〜6か月程度)、サービスの種類・頻度・利用事業所候補、連携体制、危機対応、家族支援、インフォーマル支援(地域活動・家族会等)、合理的配慮の方針等を文章化します。
本人・保護者の意思決定を尊重し、到達可能で測定可能な目標にします。
サービス担当者会議
保護者、関係事業所(児童発達支援・放デイ等)、必要に応じ学校・医療・自治体担当者が集まり、計画案を共有・調整します。
オンライン開催も可。
役割分担や情報共有のルールを明確にします。
自治体への申請・支給決定
計画案等を添えて自治体に支給申請。
自治体は必要量を審査し、支給量(利用回数・期間)を決定、受給者証を交付します。
自治体によっては「セルフプラン(保護者作成)」も認めますが、原則は相談支援専門員による作成を推奨します。
利用開始・連携支援
受給者証の範囲で各事業所の「個別支援計画」が立ち、それが障害児支援利用計画と整合するよう相談支援専門員が橋渡し・調整します。
送迎や医療との連絡、学校との合理的配慮の共有も支援します。
モニタリング(継続評価)
概ね6か月に1回以上、または生活環境の変化(就学・進学・転居・入退院など)時に面接・訪問等で進捗を確認。
必要に応じ計画を見直します。
事業所の個別支援計画の振り返りともタイミングを合わせます。
更新・再申請
受給者証の有効期間終了前に再アセスメントを行い、次期計画を策定し直します。
就学・卒業等の節目には移行支援(未就学→小学校、小→中・高、18歳以降の成人サービスへの引継ぎ)を重点化します。
計画書の主な構成
– 本人・家族のプロフィール、強みとニーズ
– 長期目標・短期目標(生活、学習、対人、行動、健康、家族支援など領域別)
– 利用サービスの種類・頻度・期間・事業所名(候補)
– 医療・療育・教育との連携方針、合理的配慮の具体
– 危機対応(問題行動のトリガーと対応、緊急連絡先)
– 家族支援(レスパイト、きょうだい配慮、保護者の相談先)
– モニタリング方法・時期、KPI(観察指標)
– 本人・保護者の同意、情報共有の範囲
障害児相談支援事業所で受けられる主なサポート
– 情報提供と制度ナビゲーション
サービスの選択肢、自己負担(基本1割+上限月額)、送迎、加算要件、地域資源の案内。
– 申請・手続き支援
受給者証の新規・更新、医師意見書の取得調整、必要書類の整備。
– 関係機関連携
学校・園との連絡会、合理的配慮の調整、医療・リハ職(PT/OT/ST)との目標共有、福祉用具・住宅改修の助言。
– 権利擁護・意思決定支援
本人の意思表出の支援、虐待や不適切対応の相談・通報支援、苦情解決の伴走。
– 家族(介護者)支援
レスパイト(短期入所・日中一時・居宅支援)の活用、きょうだい支援、経済支援制度の案内(特別児童扶養手当、医療費助成など)。
– 医療的ケア児のコーディネート
学校・園での医療的ケア体制調整、訪問看護や通所先でのケア手順の整合。
– ライフステージの移行支援
就学前の準備、進学・進級時の環境調整、18歳前後の成人サービス(計画相談支援)への切れ目ない引継ぎ。
– 危機・行動障害対応
強度行動障害に関する専門職との連携、ポジティブ行動支援(PBS)の導入調整、家庭環境の調整助言。
費用・利用要件・期間の目安
– 相談支援(計画作成・モニタリング)は利用者負担なし(公費で事業所に報酬が支払われます)。
交通費等の実費は自治体・事業所のルールにより異なります。
– サービス利用の自己負担は原則1割。
ただし世帯所得に応じた月額上限があります。
送迎や食材料費などは実費。
– 手帳の有無は必須条件ではなく、医師意見書等と総合的判断で支給決定される場合があります(自治体裁量)。
– モニタリングは概ね6か月に1回以上、受給者証の更新時(多くは1年)に再アセスメント・計画見直しを行います。
– 初回相談から利用開始までの期間は、目安で2〜6週間程度ですが、地域の混雑状況と緊急度で変動します。
実務上のポイント(利用者側の準備)
– 目標イメージを言語化しておく(例 集団での待つ時間を増やしたい、身辺自立を進めたい、登校渋りの不安軽減など)。
– 学校・園・医療の資料(個別の教育支援計画、療育評価、医師の所見)をまとめて提示。
– 平日の動線・家族の就労状況・送迎の可否を具体的に共有。
– 合理的配慮で効果があった工夫、逆に合わなかった支援も伝える。
– 情報共有の同意範囲(どこまで誰に)を事前に考える。
よくある誤解の補足
– 事業所選びは利用者の選択が基本。
相談支援事業所が特定事業所を強制することはできません。
– 相談支援は一度作ったら終わりではなく、状況に応じて変更・見直しが可能です。
– セルフプランも制度上は可能ですが、ケースが複雑な場合や連携が必要な場合には、相談支援専門員の関与が望ましいとされています。
根拠(法令・通知・ガイドライン)
– 児童福祉法 障害児通所支援や障害児相談支援の制度的枠組み(支給決定、指定制度、運営基準の根拠)。
– 児童福祉法施行令・施行規則、厚生労働省令・告示 指定障害児相談支援の人員・設備・運営基準、報酬算定構造等(平成24年の制度改正以降の告示・省令、以後の改正を含む)。
– 計画相談支援・障害児相談支援ガイドライン(厚生労働省) 本人中心のケアマネジメント手順、アセスメント項目、モニタリング頻度、サービス担当者会議の運用等(近年の改訂版 令和5年度改訂など)。
– 障害者総合支援法 未成年でも一部の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、短期入所等)の利用根拠。
成人期への移行支援の整合。
– 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 医療的ケア児の支援体制整備と自治体の責務(学校・保育等との協働に関する基本理念)。
– 各自治体の実施要綱・手引き 申請書式、セルフプランの取扱い、モニタリング運用、地域生活支援事業(移動支援・日中一時等)のローカルルール。
これらの法令・通知に基づき、相談支援専門員は「本人の最善の利益」と「家族の生活の質」を中心に、制度横断のコーディネーションを行い、計画の立案・実行・評価を継続します。
現場では、厚労省のガイドラインに沿って、ICF視点のアセスメント、具体的な目標設定、エビデンスに基づく支援(PBS等)の導入、合理的配慮の具体化、権利擁護・虐待防止の徹底、そしてライフステージに応じた切れ目ない支援を重視します。
まとめ
– 計画は、相談→アセスメント→計画案→担当者会議→自治体の支給決定→利用開始→モニタリング→見直し、という循環で作成・運用されます。
– 受けられる支援は、制度ナビゲーション、申請手続き、関係機関連携、権利擁護、家族支援、医療的ケア児の調整、移行支援、危機対応など多岐にわたります。
– 根拠は児童福祉法と関係省令・告示、厚労省ガイドライン等。
自治体要綱で実務手順が具体化されています。
実際の手続き・書式・運用の細部は自治体により異なるため、お住まいの市町村の障害福祉(こども)担当課、または身近な障害児相談支援事業所に早めに相談されることをおすすめします。
必要であれば、初回面接で使える質問リストや準備チェックリストも作成しますのでお申し付けください。
学校・医療・福祉機関との連携や日常の困りごと相談にはどこまで対応してくれるのか?
結論から言うと、障害児相談支援事業所は「障害のあるお子さんとその家族の生活全体を俯瞰し、必要な支援が適切につながるように企画・調整し、継続的に見直す」役割を担います。
学校・医療・福祉機関との連携は、保護者の同意を前提に相当広く実施できますが、法令上の役割は「調整・助言・情報連携」が中心で、診療や教育の決定権、直接の療育や介護等の「実施主体」にはなりません。
以下、できることの具体と限界、日常相談の対応範囲、根拠を詳述します。
障害児相談支援事業所の基本機能
– アセスメント(生活全体の課題・強みの把握)
– 障害児支援利用計画の作成(目標・手立て・連携先・役割分担を明記)
– 申請支援(受給者証の申請、必要書類の取得支援等)
– サービス担当者会議の開催・参加(関係者の合意形成)
– モニタリング(概ね6か月に1回以上の定期見直し+必要時の随時見直し)
– 権利擁護・苦情対応・虐待予防の視点での支援
– 進学・卒業・18歳到達などライフステージ移行の支援と引継ぎ
根拠
– 児童福祉法(障害児通所支援の枠組みと市町村による支給決定)
– 厚生労働省令「指定特定相談支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第62号。
以下「運営基準」) アセスメント、計画作成、担当者会議、モニタリング、関係機関連携、個人情報管理、苦情対応などの必須事項を規定
– 計画相談支援・障害児相談支援ガイドライン(厚生労働省通知) 生活全体を対象とする支援、関係機関連携、移行支援等の実務指針
学校との連携はどこまで可能か
できること
– 学校との情報共有・意見交換(保護者の同意に基づいて、担任、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー等と連絡調整)
– 校内会議・支援会議等への参加・同席(就学支援委員会、個別の教育支援計画・個別の指導計画の策定会議等に招かれた場合)
– 合理的配慮の検討支援(学習環境やコミュニケーション配慮、行動上の支援、通級・加配・ICT活用等の具体案を整理し学校側と協議)
– 保育所等訪問支援や通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)との整合(学校での目標・配慮と、福祉側の個別支援計画をすり合わせ、切れ目のない支援に)
– 進学・転校・就学先決定の場面での伴走(情報整理、見学・相談の段取り、関係機関連携)
限界(できないこと)
– 学校の最終的な教育上の判断(クラス編成、学級形態、就学先の決定等)を指示・決定する権限はない
– 学校内での直接的な支援提供者にはならない(教室内での常時支援は保育所等訪問支援など該当サービスの領域)
– 法的代理や不服申立ての代理はできない(必要に応じて教育委員会・弁護士・第三者機関の紹介や情報提供を行う)
根拠
– 運営基準 教育・保健・医療・福祉等の関係機関との密接な連携に努める義務
– 障害者差別解消法 学校等公的機関には合理的配慮の提供義務。
相談支援はその調整・助言を担う実務
– ガイドライン 就学・進学など移行期における計画的連携の必要性
医療機関との連携はどこまで可能か
できること
– 医師・療法士(PT/OT/ST)・臨床心理士等との情報共有とケース会議(診断名や所見、療育上の留意点を計画に反映)
– 受給者証申請に必要な医師意見書・診断書の取得支援(様式案内、必要事項の説明、日程調整)
– 通所リハや外来訓練のスケジュールと福祉サービスの両立調整
– 入院・長期欠席時の連携(退院後の在宅支援体制づくり、医療的ケア児の場合の訪問看護・居宅での体制調整)
限界(できないこと)
– 医療行為・診療の指示や内容決定はできない
– 医薬品・治療法の専門的指示や個別の医学的判断は行わない(必要時は主治医等へ照会・同席支援)
根拠
– 運営基準 保健・医療機関との連携
– 医療の決定権は医師法等に基づく医療機関側の権限
– 入院時情報連携に関する加算等(報酬通知)に示される連携の必要性
福祉機関・行政との連携はどこまで可能か
できること
– 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイ、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援など)の選定・調整
– 必要に応じて障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、移動支援等)や地域生活支援事業、各種手当・給付(特別児童扶養手当、日常生活用具等)へのつなぎ
– 申請手続きの案内・同行・文書作成支援(市町村の支給決定事務との調整)
– 苦情やトラブルの一次調整(サービス事業所との利用調整、契約・支援内容の見直し協議)
限界(できないこと)
– 行政の支給決定権限の代行はできない(あくまで申請・調整支援)
– 相談支援事業所自身が通所支援や居宅介護を直接実施するわけではない(ただし同法人内に複数事業がある場合は利益相反に配慮)
根拠
– 児童福祉法(障害児通所支援の支給決定は市町村の権限)
– 運営基準 サービス担当者会議の開催、関係機関連携、苦情対応
– ガイドライン 生活全般(制度外資源も含む)へのつなぎを求める趣旨
日常の困りごと相談の対応範囲
対応できる内容(例)
– 生活リズム(睡眠・食事)、排泄、身辺自立、感覚過敏・偏食、登校しぶり、家庭内コミュニケーション、きょうだい関係
– 行動上の困難(かんしゃく、他害・自傷、こだわり)への環境調整や支援手立ての助言、専門機関の紹介
– 保護者のメンタルケアにつながる情報提供(親の会、ペアレントトレーニング、相談機関の案内)
– 学校・保育園・通所事業所との情報整理と一貫した支援方針づくり
– 福祉用具・日常生活用具、交通・送迎、金銭・福祉制度の情報提供
– 虐待の兆候や権利侵害の察知と適切な機関連絡(児童相談所・市町村・警察等)
限界
– 臨床的な診断・評価や専門的トレーニングの実施はしない(必要に応じて医療・療育機関へつなぐ)
– 24時間の緊急対応や常時相談窓口ではない(自治体の夜間・休日窓口や児童相談所の虐待ホットライン等を案内)
– 家庭内のトラブル介入については安全確保を最優先に、関係機関と連携して対応(単独での即時解決を約束はできない)
根拠
– 運営基準・ガイドライン 相談支援は生活全般を対象とし、必要な支援につなぐ中核機能を担うこと、権利擁護・虐待防止の観点を明示
– 児童虐待の防止等に関する法律 虐待が疑われる場合の通告義務
情報共有と同意、プライバシー
– 連携は保護者(原則として本人を含む)の同意に基づいて実施。
書面同意や同意範囲の明確化が原則
– 目的外利用・第三者提供の制限、記録の保存、個人情報保護に関する規程整備が義務
根拠
– 運営基準 個人情報の適切な取扱い
– 個人情報の保護に関する法律
相談の流れと頻度
– 初回相談→アセスメント→障害児支援利用計画(案)作成→市町村に申請→支給決定→サービス担当者会議→利用開始→モニタリング(概ね6か月ごと、必要時は随時)
– 状況悪化、入退院、進学・転居等のライフイベント時は臨時の見直し会議を速やかに開催
根拠
– 運営基準 計画作成・担当者会議・モニタリングの実施
費用と利用のしやすさ
– 相談支援(計画作成・モニタリング等)自体は原則として利用者負担はありません(公費による給付)。
ただし自治体の運用や交通費等の実費は地域差あり
– 事業所は予約制が一般的。
訪問・オンライン面談に対応する事業所もあります
18歳到達・卒後の移行支援
– 18歳以降は「特定相談支援(計画相談支援)」に切替。
スムーズに引き継げるよう、在学中から就労・進学・日中活動・居住の見通しを盛り込む
根拠
– ガイドライン 切れ目ない相談支援とライフステージ移行支援の明記
– 相談支援事業の区分(障害児相談支援と特定相談支援)の制度設計
実務上のポイント(利用者側の目線)
– 連携してほしい相手・共有してよい情報の範囲を事前に事業所へ明確に伝える
– 学校会議や病院受診の予定が決まったら早めに相談支援専門員へ共有(同席や事前打合せがしやすくなる)
– 困りごとは「場面・頻度・きっかけ・対応結果」をメモして見せると、支援策が具体化しやすい
– 事業所選びは、児童領域の経験、学校・医療との連携実績、緊急時の連絡体制、利益相反に配慮した運営などを確認
主要な根拠・参照先(名称)
– 児童福祉法(障害児通所支援・相談支援の枠組み、支給決定は市町村の権限)
– 厚生労働省令「指定特定相談支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第62号)
– 計画相談支援・障害児相談支援ガイドライン(厚生労働省通知、最新版は令和期に改訂)
– 障害者差別解消法(合理的配慮)
– 児童虐待の防止等に関する法律(通告義務)
– 個人情報の保護に関する法律(個人情報の適正管理)
まとめ
– 相談支援事業所は、学校・医療・福祉を横断する「調整役」として、保護者の同意のもと相当広い連携と日常相談に対応できます。
– 一方で、医療や教育の決定権や直接の療育・介護の実施は権限外。
役割は「つなぐ・整える・見直す」ことにあります。
– 根拠は児童福祉法、運営基準省令、厚労省ガイドライン等に明確化されています。
実際の運用は自治体や事業所で差があるため、具体的な連携方法・頻度は担当の相談支援専門員と合意形成して進めるのが確実です。
利用開始までの流れや費用、事業所の選び方はどうすればよいのか?
以下は、日本の「障害児相談支援事業所」(指定障害児相談支援)の役割、利用開始までの流れ、費用、選び方のポイントを、根拠も交えながら詳しくまとめたものです。
自治体の実務運用で細部が異なる場合があるため、最終確認はお住まいの市区町村窓口や希望する事業所にご相談ください。
障害児相談支援事業所でできること(役割・支援内容)
– サービス等利用計画の作成と見直し
– お子さん・保護者の思い、現在の生活や特性、課題、強みをアセスメントし、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、必要に応じて短期入所などの利用方針・目標・回数案を「サービス等利用計画」にまとめます。
– 少なくとも6カ月に1回以上のモニタリング(継続支援)を行い、目標やサービス量の妥当性を見直します。
– 申請・支給決定に向けた伴走
– 市区町村への支給申請に必要な書類(計画案、医師意見書等の必要書類の確認)の準備を支援。
受給者証が発行されるまでの調整や問い合わせにも対応します。
– 事業所・関係機関連携とコーディネート
– 児童発達支援、放デイ、医療、保育所・幼稚園・学校、相談窓口(発達相談、子ども家庭総合支援など)、地域生活支援事業(移動支援・地域活動支援センター等)との連絡調整。
– サービス担当者会議の開催・司会進行(教育・医療・福祉の三者以上での情報共有と役割分担を調整)。
– 権利擁護と家族支援
– 虐待防止・差別の防止、合理的配慮の相談、きょうだい支援、レスパイト(短期入所など)の活用、就学・進学・学校内支援体制(個別の教育支援計画等)との接続支援、医療的ケア児の地域支援調整。
– 制度・資源の案内
– 障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳等)や特別児童扶養手当、補装具・日常生活用具、交通・医療費助成、障害年金(将来展望)、移行期(成人期)支援の見通しづくり。
– サポートブックや記録の整備支援
– サポートブック・プロフィールシートの作成支援、関係機関連携に必要な同意や情報の整理。
利用開始までの流れ(目安の期間を含む)
– 相談・問い合わせ
– 市区町村の障害福祉窓口の事業者一覧や、学校・医療機関・地域の相談窓口から紹介を受け、候補事業所へ連絡。
空き状況、対応範囲、得意分野を確認します。
– 初回面接・契約
– 重要事項説明(個人情報、苦情解決、解約、守秘義務等)を受け、同意のうえ契約。
現状や困りごと、希望を丁寧に聴取します。
所要1~2回の面接が多いです。
– アセスメントと計画案(サービス等利用計画案)の作成
– 自宅や学校・園の訪問を含むこともあり、ICFの観点(生活機能・活動・参加・環境因子)で整理。
通常1~2週間程度で計画案を作成。
– 市区町村へ支給申請
– 計画案、医師意見書や手帳等の証明書類(自治体指定)を添えて申請。
やむを得ない事情での猶予・特例がある自治体もありますが、原則は計画の提出が必要です。
– 支給決定・受給者証の交付
– 審査期間は概ね1~4週間。
決定量(利用日数・回数等)と有効期間が記された受給者証が交付されます。
– 事業所選定・担当者会議・利用開始
– 計画に基づき、具体的な事業所と契約。
サービス担当者会議で役割と連携体制を確認後、利用開始。
– 継続モニタリング・計画見直し
– 少なくとも6カ月に1回、または進学・進級・状態変化時に見直し。
更新時は市区町村への手続きを伴います。
注意
– 期間は自治体や書類準備の状況、医師意見書の取得状況に左右されます。
入園・入学期は混み合いやすいため、2~3カ月程度の余裕を見て早めの相談が安全です。
– セルフプラン(家族が計画を自作)を認める自治体もありますが、専門的なアセスメントや連携調整が受けにくく、見直し・更新で負担が大きくなりがちです。
事業所の支援を受けることが一般的です。
費用(自己負担と無料になるもの)
– 相談支援(計画作成・モニタリング)の自己負担
– 障害児相談支援の利用者負担は原則ありません。
相談支援給付として市区町村が事業所へ公費(給付)で支払います。
家族に相談料はかかりません。
– 例外的に、事業所の判断で発生する実費(遠方出張の交通費等)をお願いされるケースがまれにありますが、重要事項説明書で説明・同意が必要です。
– 通所系サービス等の自己負担
– 児童発達支援、放課後等デイサービスなどを実際に利用する際は、世帯の所得に応じた「利用者負担上限月額」が適用され、同月内の合算自己負担は上限までとなります。
– 一般的な上限区分の例(自治体で告示・運用)
– 生活保護世帯 0円
– 市町村民税非課税世帯 0円~低額(多くは0円)
– 一般1(所得割が一定以下) 低額上限(子どもは成人より低い上限が設定される運用が一般的)
– 一般2(一定以上) 高額上限(例 3万7千円台)
– おやつ代・食材料費・教材費・行事費・送迎の一部などは「実費負担」として別途かかることがあります。
金額や取り扱いは各事業所で異なります。
事業所の選び方(チェックポイント)
– 得意分野・経験
– 発達障害、重症心身障害、医療的ケア児、強度行動障害、きょうだい支援、虐待や家族支援など、ニーズに合った経験を持つか。
– 相談支援専門員が「相談支援従事者研修(初任者・現任者)」を修了しているか、強度行動障害支援者養成研修など加算要件となる専門研修を修了しているか。
– 連携力・調整力
– 学校・園、医療、通所事業所と担当者会議を実施し、記録・議事録の整備、役割分担の明確化ができるか。
教育分野の会議(個別の教育支援計画等)と情報連携できるか。
– 面接・訪問のスタイル
– 自宅・学校・医療機関への訪問の可否、オンライン併用、平日夕方や土曜の面接可否、緊急時の連絡先、レスポンスの早さ。
– 中立性・透明性
– 同一法人が通所サービス(放デイ等)も運営している場合、中立性をどう担保するか。
複数事業所からの選択肢提示、同意文書の扱い、苦情対応の仕組みが明確か。
– 体制・担当件数
– 相談支援専門員の人数、1人当たりの担当件数、引継ぎ・不在時のバックアップ体制、個人情報保護・同意取得の運用。
– モニタリングの質
– 目標・成果の確認(利用満足だけでなく、参加や行動、家族負担軽減などの指標)、ICFの視点、見直しのタイミング、文書のわかりやすさ。
– 利用者の声・評判
– 自治体の第三者評価、相談支援に関する地域の協議会への参加状況、学校・医療機関からの評価、実際の利用者の感想。
よくある質問・注意点
– 診断や手帳がなくても相談できるか
– 相談は可能です。
受給者証の支給決定には、医師意見書や手帳等の客観的資料が求められるのが一般的です。
基準は自治体ごとに異なるため早めに確認を。
– 受給者証の更新
– 有効期間は通常1年程度。
更新時はモニタリング結果や計画の見直しが必要です。
期限の1~2カ月前から準備を始めると安心です。
– サービスが合わないと感じたら
– 相談支援専門員に早めに共有し、計画見直しや事業所変更、利用回数の調整などを検討。
解約・乗り換えの手順や同意書類の扱いも事前に確認を。
– セルフプランの可否
– 認められている自治体もありますが、専門的支援・連携が受けられないため、初めての方や支援の組み合わせが多い方は相談支援の利用が推奨されます。
根拠・参照(制度・ガイドラインの位置づけ)
– 法的根拠・制度
– 児童福祉法に基づく障害児通所支援・入所支援の枠組み、及び障害児相談支援(相談支援給付)の規定。
市区町村が支給決定(受給者証交付)を行うこと、計画に基づく利用とすることが定められています。
– 相談支援専門員の配置・研修、運営基準、モニタリングや会議の実施、記録・個人情報保護等は厚生労働省の告示・通知(指定基準・運営基準・報酬算定要件)で具体化されています。
– ガイドライン・手引き
– 厚生労働省「計画相談支援(障害児相談支援を含む)ガイドライン」や「障害児通所支援の手引き」等で、アセスメントの視点、サービス等利用計画の標準様式、モニタリング周期(少なくとも6カ月に1回以上)、サービス担当者会議の役割、連携のあり方が示されています。
– 利用者負担上限月額や世帯区分の取扱いは、厚生労働省通知および各自治体の要綱・パンフレットで示されます。
子どもの区分では一般に成人より低い上限が設定されています。
– 代表的な確認先
– お住まいの市区町村 障害福祉課(障害児通所支援の案内、指定事業所一覧、申請様式、負担上限月額の区分・額)
– 都道府県・指定都市の福祉主管課(相談支援従事者研修、運営基準の周知)
– 厚生労働省 公式資料(通知・手引き・Q&A)
まとめ
障害児相談支援事業所は、単にサービス利用の手続きを手伝う場ではなく、暮らしと学び全体を見通し、関係機関をつなぎ、家族に伴走する「地域連携のハブ」です。
最初の相談からサービス開始までは1~2カ月程度が目安ですが、入学期などはさらに時間を要することがあります。
相談支援自体の自己負担は原則不要で、通所サービス等の自己負担は世帯の所得に応じた上限月額の範囲になります。
事業所選びでは、得意分野、連携力、中立性、担当体制、モニタリングの質を重視し、複数社を比べることをおすすめします。
最終的な要件や書式、費用区分は自治体で異なるため、早めに窓口で最新情報をご確認ください。
【要約】
障害児相談支援事業所は、障害のある子どもと家族の地域のハブ。相談受付からアセスメント、計画作成、受給者証申請支援、事業所選定・会議調整、定期モニタリング、権利擁護や就学・成人移行まで一貫伴走。療育や診断は行わず、サービス量の決定は市町村。相談・計画・調整は原則無料。
オーパコラム vol.3
オーパ利用についてはお気軽にお問合せください。