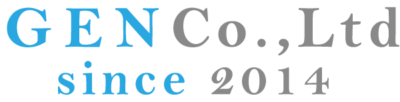放課後等デイサービスと障害児相談支援は何が違い、どんな支援が受けられるのか?
要点のまとめ
– 放課後等デイサービス=学校に通う障害のある子どもの「療育・生活訓練・余暇支援」など直接支援を行う通所サービス(現場で子どもに関わる支援)。
– 障害児相談支援=ご家庭のニーズ把握から計画作成、サービス調整・見直しまでを担う「計画相談・コーディネート」(支援の設計図づくりと伴走)。
– 位置づけ=どちらも児童福祉法に基づく公的サービス。
市町村の支給決定(受給者証)により利用。
放課後等デイは「障害児通所支援」の一つ。
障害児相談支援は「計画相談支援(児童)」。
それぞれの目的と役割の違い
– 放課後等デイサービス
– 目的 学齢期(小学生〜高校生相当)の障害のある子どもが、放課後や長期休暇中に安心して過ごし、生活動作や社会性、コミュニケーション、感覚・運動などの発達を促す「療育(リハビリテーションを含む広義の支援)」と、社会参加・余暇活動を提供すること。
– 役割 個別支援計画に基づく個別療育・小集団活動、日常生活訓練、学習・就学支援の補完、地域・学校・家庭との連携、保護者支援、送迎などの直接支援を行う。
– 障害児相談支援
– 目的 子どもと家族の生活全体を見立て、必要な福祉・医療・教育・就労準備等の資源を組み合わせる計画を作成し、実行・見直しを継続的に支えること。
– 役割 アセスメント(ニーズ把握)、障害児支援利用計画の作成、サービス担当者会議の開催、利用調整、モニタリング・評価、危機対応、権利擁護、進学・卒後(成人期)への移行支援など、ケアマネジメント機能を担う。
受けられる主な支援内容
– 放課後等デイサービス(施設・事業所で提供)
– 個別療育 生活動作(食事・更衣・清潔)練習、認知・言語、感覚統合、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、行動支援等。
– 集団活動 協働・ルール学習、対人関係づくり、遊びや余暇の拡大、地域交流。
– 学校生活の補完 宿題の見守り、学習の進め方の工夫、合理的配慮の学校連携。
– 運動・健康 体幹・粗大運動、微細運動、リラクゼーション、体力づくり、感情の自己調整スキル。
– 社会参加・外出 買い物訓練、公共交通機関の利用体験、地域イベント参加。
– 医療的ケアへの対応 必要に応じ看護職配置や嘱託医連携のもと吸引・経管栄養等(所要の体制がある事業所に限る)。
– 家族支援 保護者面談、ペアレントトレーニング的な助言、家庭での工夫の提案、関係機関連携。
– 送迎 学校・自宅間の送迎(事業所と契約内容により実施)。
– 計画と振り返り 児童発達支援管理責任者がアセスメント→個別支援計画を作成し、おおむね6か月ごとにモニタリング・見直し。
– 障害児相談支援(相談支援事業所が提供)
– 初回アセスメント 生活・発達・行動・家族状況・学校等の情報整理、困りごとの言語化。
– 障害児支援利用計画の作成 目標設定(短期・中期)、利用サービス(放課後等デイ、児童発達支援、保育所等訪問支援、短期入所、居宅系、地域資源等)の組合せ設計。
– サービス担当者会議 学校・医療・事業所・自治体との情報共有と役割分担の明確化。
– 利用調整と手続き支援 事業所の紹介・見学調整、受給者証申請の助言、待機時の代替案提示。
– 定期モニタリング 3〜6か月程度ごとに計画の効果検証・修正、加配や合理的配慮の相談。
– 危機・トラブル対応 行動の強い問題、登校しぶり、家庭の負担増などの際の緊急調整。
– 権利擁護と情報提供 相談窓口や助成制度の案内、虐待防止の観点、苦情解決支援。
– ライフステージ移行 進学・高校卒業前後の移行期支援(就労移行・生活介護等、成人サービスへの橋渡し)。
対象者・利用時間・場所の違い
– 対象
– 放課後等デイ おおむね小1〜高3相当の障害のある児童。
医師の診断や特別児童扶養手当等の受給状況、発達特性の所見などを基に自治体が総合判断。
– 相談支援 障害児通所支援等の利用を希望する全ての障害のある児童・家族(年齢下限は実務上なし。
未就学でも対象。
)
– 利用の場・時間
– 放課後等デイ 事業所に通所(放課後、長期休暇は日中)。
1回あたり2〜3時間程度が一般的(事業所により異なる)。
– 相談支援 相談支援事業所・家庭・オンライン等で面接。
計画作成・会議・モニタリングは必要時に実施。
利用までの流れ(典型)
– 相談(地域の相談支援事業所・自治体窓口・こども家庭支援系窓口)
– 障害児相談支援の契約→アセスメント→障害児支援利用計画(案)作成
– 市町村へ申請→支給決定→受給者証の交付
– 放課後等デイ等の事業所と契約・個別支援計画策定→利用開始
– 定期モニタリング(相談支援)と個別支援計画の見直し(事業所)
費用負担
– 放課後等デイ 原則1割の自己負担。
世帯所得に応じた月額上限あり(例 住民税非課税世帯は0円、一般所得層は約4,600円、一定以上の所得は約37,200円の上限が目安)。
おやつ代・教材費等の実費は別途ありうる。
– 障害児相談支援 計画相談そのものの利用者負担は基本的に発生しない(公費負担)。
併用・組み合わせの考え方
– 放課後等デイは、以下のサービスと組み合わせることで効果や家族負担の軽減を図れる。
– 児童発達支援(未就学向け、就学後は放課後等デイへ移行が一般的)
– 保育所等訪問支援(幼稚園・学校・保育所へ専門職が訪問し助言)
– 居宅訪問型児童発達支援(外出困難な重症心身障害児等への訪問療育)
– 短期入所(ショートステイ)、日中一時支援(自治体事業)
– これらの選択と調整の中核を担うのが障害児相談支援(計画相談)。
質の担保と事業所選びのポイント
– 放課後等デイ
– 児童発達支援管理責任者の配置とアセスメントの質
– 個別支援計画の具体性(評価指標・期間・家庭連携の記載)
– 職員の資格・研修・定着、支援アプローチ(構造化、PBS、SST等)の妥当性
– 学校・医療・相談支援との連携体制、記録・振り返り
– ガイドラインに基づく自己評価の公表、有事の安全管理、送迎の安全
– 障害児相談支援
– 相談支援専門員の経験・研修受講状況(児童領域の知見)
– アセスメントの丁寧さと家族の合意形成力
– 会議運営・連携力、危機対応、移行支援の実績
根拠(法令・指針等)
– 児童福祉法
– 障害のある児童に対する通所支援(障害児通所支援)として放課後等デイサービス・児童発達支援等を位置付け。
– 市町村による支給決定、受給者証の交付、利用者負担(給付費の一部負担・上限)の仕組みを規定。
– 児童福祉法施行令・施行規則、厚生労働省令・告示
– 障害児通所支援の指定基準・人員設備・運営基準、報酬(区分・算定要件)、相談支援(障害児相談支援)の運営基準等を詳細に規定。
– 放課後等デイサービスガイドライン(厚生労働省)
– 事業所の運営方針、アセスメント・個別支援計画の作成と評価、家族支援、学校等との連携、自己評価の公表など、質の確保・向上のための標準を提示。
最新版は適宜改定。
– 障害児相談支援に関する通知・Q&A(厚生労働省)
– 計画相談の対象、手続、モニタリング、サービス担当者会議の位置づけ、成人期サービスへの移行支援等の運用を明確化。
– 収入に応じた利用者負担上限
– 児童福祉法に基づく給付の利用者負担の考え方を定めた国の告示・通知および各自治体運用。
よくある疑問
– 相談支援を使わずに放課後等デイを契約できるか?
– 原則、障害児通所支援の新規利用や変更時には障害児支援利用計画の提出が求められ、障害児相談支援の利用が推奨・事実上必要です(自治体運用で例外・簡素化がある場合もあり)。
– 学習塾のような学習のみの支援は可能か?
– 放課後等デイは福祉の「療育」サービスであり、教育や塾の代替ではありません。
学習はあくまで生活・社会参加に資する支援の一環として位置づけられます。
– 医療的ケア児は利用できるか?
– 可能ですが、事業所に必要な体制(看護職配置・研修・医療連携等)が備わっていることが条件です。
事業所ごとに受け入れ可否が異なります。
まとめ(違いの要点)
– 放課後等デイサービスは「現場の療育・日常生活支援」を提供する通所サービス。
– 障害児相談支援は「計画づくりとサービス調整」を担う相談・ケアマネジメント。
– 両者は相補的で、相談支援が全体設計を行い、放課後等デイが現場で実行し、双方が連携して定期的に見直す仕組み。
児童福祉法および厚生労働省の基準・ガイドラインに根拠があり、市町村の支給決定を経て公費で利用できます。
注意
– 具体的な利用条件・負担上限・算定要件・提供時間帯・送迎可否等は、年度の報酬改定や自治体の運用で差があります。
最新情報はお住まいの市町村窓口、相談支援事業所、または厚生労働省の最新通知・ガイドラインをご確認ください。
対象年齢・発達特性・利用上限・料金などの利用条件はどうなっているのか?
以下は、ブログでよく検索される「放課後等デイサービス」「障害児相談支援」に関する利用条件(対象年齢・発達特性・利用上限・料金など)を、根拠とともにまとめた解説です。
自治体運用や最新の報酬・通知の改定で細部が変わることがあるため、最終確認はお住まいの市区町村または事業所・相談支援専門員にご相談ください。
放課後等デイサービス(障害児通所支援)の利用条件
– 制度の位置づけ
– 児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の一類型です。
就学している障害のあるお子さんに、放課後や長期休暇中に療育・社会参加支援・余暇支援などを提供します。
– 指定事業所は、厚生労働省令による人員・設備・運営基準を満たして指定を受けます。
対象年齢・対象者
原則 小学校1年生から高校生相当の就学児(おおむね6~18歳)。
対象となる障害種別 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・難病等。
医療的ケア児も、医療的ケア体制のある事業所で受入れ可能な場合があります。
利用には市区町村が発行する「障害児通所受給者証」が必要です。
障害者手帳の有無のみで判断されるわけではなく、医師意見書・特別支援教育の状況・生活状況など総合的に勘案されます。
年齢の取扱いの補足 基本は18歳到達までが対象ですが、「高校在学中に18歳を超える」などの個別事情がある場合の扱いは自治体判断(支給決定)に委ねられることがあります。
発達特性への適合
発達障害(ASD、ADHD、LDなど)や軽度~中等度の知的障害、情緒面の課題、コミュニケーションや集団適応の困りごと等、幅広い特性に対応します。
ただし事業所ごとに得意領域(例 運動療育、SST、学習支援、感覚統合、行動支援、医療的ケア対応など)が異なるため、個別支援計画と事業所の強みが合致しているかが重要です。
利用上限(回数・時間・定員)
回数上限(支給量) 受給者証に「月◯日」等の支給量が記載され、市区町村がガイドラインに沿って決定します。
決定にあたっては、学校・家庭の状況、他サービス(児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅介護など)とのバランス、本人の状態像や目標が総合的に勘案されます。
利用時間帯 原則は「学校終了後」。
学校休業日(夏休み等)は日中の利用が可能です。
1回あたりの提供時間は事業所の提供時間数に準じます(長期休暇中は長時間枠を設ける事業所もあります)。
事業所の定員 各事業所は指定時に1日あたりの定員を定めており、定員超過の受入れはできません。
待機が発生する地域もあります。
併用・組合せ 放課後等デイサービスは、他の障害児通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援)や福祉サービスと併用可能ですが、総枠(支給量)内での利用となります。
料金(自己負担)
基本 児童福祉法に基づく給付で、原則1割の自己負担。
ただし世帯の所得区分に応じて「月額の負担上限」が設けられています。
実際の負担は「自己負担1割と実費」を合算しつつ、自己負担分は上限月額を超えません。
代表的な上限月額(目安)
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(低所得) 0円
一般1(市町村民税課税・所得割が一定額未満。
年収目安として約890万円未満など自治体が示すことあり) 月4,600円
一般2(上記以上) 月37,200円
世帯の合算適用 同一世帯で複数の障害福祉サービス(児童の通所支援を含む)を利用しても、自己負担分は世帯の「負担上限月額」を超えません。
実費負担 おやつ代、教材費、行事費、給食費、交通費等は実費で、上限月額の対象外です(徴収の有無と金額は事業所規程による)。
送迎自体は給付対象ですが、実費相当の徴収ルールを設けている自治体・事業所もあります。
減免・例外 多子世帯の配慮や独自減免を設ける自治体もあります。
必ず自治体窓口で最新の基準をご確認ください。
利用手続きの流れ(概要)
1) 市区町村の相談窓口または指定特定相談支援(障害児相談支援)へ相談
2) サービス等利用計画(計画相談)を作成(後述)
3) 市区町村が支給決定(受給者証発行、支給量を記載)
4) 事業所と契約・個別支援計画の策定・利用開始
多くの自治体で、計画相談(相談支援専門員による計画)を経ることが原則となっています。
やむを得ない場合の例外(セルフプラン)を認める自治体もありますが、近年は専門職による計画策定の重要性が強調されています。
障害児相談支援(計画相談支援 児童)
– 制度の位置づけ・役割
– 障害のある子どもとその家族が地域で適切な支援を受けられるよう、サービス等利用計画の作成、関係機関との連絡調整、定期的なモニタリングを行う「中核」的な相談支援です。
– 放課後等デイサービスや児童発達支援等の利用にあたり、原則としてこの計画が求められます。
対象年齢・対象者
未就学から高校生相当までの「障害児」全般が対象。
障害種別は問いません(発達障害、知的・身体・精神、難病、医療的ケア児等を含む)。
家族支援(保護者支援)や地域資源のコーディネートも重要な役割です。
利用上限・頻度
相談支援そのものに「回数上限」や自己負担は通常ありません(公費で賄われます)。
モニタリングは原則6か月ごと等の基準があり、必要に応じて随時見直しを行います(自治体の運用要領・厚労省通知に準拠)。
料金
利用者負担は原則なし(無料)。
交通費等の実費をお願いするケースがあるかは事業所規程によります。
手続き・関与場面
新規利用時のアセスメント、サービス等利用計画の作成
受給者証の更新、支給量の見直し時の意見書・モニタリング
学校・医療・福祉・就労準備(移行期)など多機関連携の調整
家族のレスパイトや公的制度・手当の案内、地域資源の紹介
典型的な「利用上限」の具体像(イメージ)
– 市区町村が示す支給決定ガイドラインに基づき、例として「月8~12日」などの支給量が決まることがあります。
就学状況、家族の就労、本人の課題・目標、他サービスの利用状況などで上下します。
– 長期休暇中は日数・時間の配分を調整することがあります。
学期中と休暇中で支給量を分けて決定する自治体もあります。
– 複数事業所の併用は可能ですが、合計が受給者証の支給量を超えない範囲で調整されます(相談支援専門員が調整・計画化します)。
根拠(法令・通知・基準の大枠)
– 児童福祉法
– 放課後等デイサービス(障害児通所支援の一類型)
– 障害児相談支援(計画相談支援 児童)
– 児童福祉法施行規則、および「指定障害児通所支援事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)
– 事業所の人員配置(管理者、児童指導員・保育士、機能訓練担当等)、面積・設備基準、運営基準等
– 「障害児通所給付費等の算定に関する基準」(厚生労働省告示)および関連通知
– 基本報酬、加算・減算、提供時間数区分、欠席時対応等の算定要件
– 「障害児相談支援の運営基準」(厚生労働省令)および手引き
– アセスメント、計画(サービス等利用計画)策定、モニタリング頻度、関係機関連携の在り方
– 利用者負担の根拠
– 児童福祉法および関係政省令、厚生労働省通知(障害福祉サービス等の利用者負担の取扱い)
– 市町村民税の課税状況(所得割額)に基づく区分と「負担上限月額」の設定
– 最新動向
– 令和6年度(2024年度)障害福祉サービス等報酬改定や、厚生労働省の「障害児通所支援の手引き」「障害児相談支援の手引き」等の見直しにより、算定や運用の細目が更新されることがあります。
よくある質問(FAQ)
– Q 受給者証がなくても見学や体験はできる?
– A 事業所の判断で見学・無料体験を受け付けることはありますが、継続的な利用には受給者証が必須です。
– Q 手帳がないと利用できない?
– A 手帳の有無のみで可否は決まりません。
医師意見書や教育・生活状況を踏まえ、市区町村が総合判断します。
– Q 兄弟で利用すると負担は増える?
– A 自己負担は「世帯の上限月額」で頭打ちになります。
兄弟で複数サービスを使っても、合算で上限を超えません(実費は別途)。
– Q 引っ越しするとどうなる?
– A 受給者証は自治体ごとの発行のため、転居先で再申請や切替え手続きが必要です。
早めに相談支援専門員に相談を。
まとめ(要点)
– 放課後等デイサービスは、就学期(概ね6~18歳)の障害のある子が対象。
利用には受給者証が必要で、月あたりの「支給量(回数)」が市区町村により決定されます。
– 自己負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた「負担上限月額(0円/4,600円/37,200円)」があり、上限を超える自己負担は発生しません。
おやつ代等の実費は別途。
– 障害児相談支援(計画相談支援)は、サービス等利用計画の作成・調整・モニタリングを担い、利用者負担は原則ありません。
放課後等デイサービスの利用にあたり、原則としてこの計画を作成します。
– いずれも詳細は法令・告示・手引き・自治体要綱に基づくため、地域差や最新改定の影響があります。
最終判断は自治体の支給決定により行われます。
参考・確認先(実務での根拠確認に有用)
– 児童福祉法・同施行規則
– 指定障害児通所支援の人員・設備・運営基準(厚生労働省令)
– 障害児通所給付費の算定に関する基準(厚生労働省告示)および各年の報酬改定資料
– 障害児通所支援の手引き/障害児相談支援の手引き(厚生労働省)
– 自治体の「障害児通所支援支給決定ガイドライン」「利用者負担上限月額のご案内」
上記を押さえておけば、「対象年齢」「発達特性」「利用上限」「料金(自己負担と上限月額、実費)」という検索キーワードで求められる情報を、根拠に基づいて過不足なく発信できます。
実際の運用は事業所の体制や自治体判断に左右されるため、記事内には「最新情報は自治体・事業所へ確認を」と明記するのがおすすめです。
受給者証の取得から事業所見学・体験・契約まで、利用開始までの手続きはどう進むのか?
放課後等デイサービス(以下、放デイ)の利用は、「受給者証(障害児通所受給者証)」の取得が前提になります。
ここでは、初めての方がつまずきやすいポイントを避けながら、受給者証の申請・取得から、事業所の見学・体験、契約、そして実際の利用開始までの全体像と実務の流れを、根拠(法令・通知・制度の位置づけ)も交えて分かりやすく整理します。
全体の流れ(まずは俯瞰)
– 相談窓口へ初回相談(自治体または障害児相談支援)
– 事業所の情報収集・見学・体験
– 相談支援事業所(障害児相談支援)と契約・アセスメント
– 障害児支援利用計画案の作成(セルフプランも可だが原則は専門職の関与)
– 市町村へ受給者証の申請
– 市町村の調査・審査・支給決定(利用量・期間の決定)
– 受給者証の交付
– 放デイ事業所との契約・個別支援計画の作成
– 利用開始(送迎や学校連携のセットアップ)
目安期間 概ね3~8週間(自治体や必要書類の準備状況により前後)
各ステップの詳しい進め方
ステップ1 初回相談(自治体・相談支援へ)
– 連絡先 お住まいの市区町村の障害福祉課・こども家庭課・障害児支援担当、または特定相談支援事業所(障害児相談支援)にまず相談。
– 目的 支援の必要性の確認、対象サービスの整理(放デイ以外に児童発達支援、居宅訪問、短期入所等の選択肢整理)、申請に必要な書類や手順の確認。
– 初回に確認されやすいこと
– 年齢・障害特性・学校状況(支援学級・通級の有無等)
– 医師の意見書・診断の有無(発達障害等を含む)
– 家族の就労状況・放課後の見守り体制
– 希望するサービスの頻度・曜日・送迎希望
ステップ2 事業所の情報収集・見学・体験
– 情報収集 自治体の「指定障害児通所支援事業所一覧」、事業所のウェブサイト、相談支援専門員からの紹介。
– 見学時のチェックポイント(例)
– 事業所の支援方針・加算体制(人員配置、療育プログラム、個別支援の手厚さ)
– 児童発達支援管理責任者(児発管)の体制と面談・評価の流れ
– 学校・家庭との連携、記録・フィードバックの方法(連絡帳、面談頻度)
– 送迎範囲・安全管理(ルート、同意書、欠席連絡ルール)
– 医療的ケアへの対応可否、アレルギー対応
– 空き枠、曜日の柔軟性、長期休暇(夏休み等)の受け入れ体制
– 体験利用 受給者証が未交付でも「見学・体験」は可能な場合が多い(ただし正式な給付対象外のため無料体験や自費扱い等、各事業所ルールを要確認)。
ステップ3 障害児相談支援(計画相談)との契約・アセスメント
– なぜ必要?
原則として、受給者証の支給決定に先立ち「障害児支援利用計画案」の提出が求められます。
専門職(相談支援専門員)によるアセスメント・計画は、適切な支給量・サービス種別の判断の根拠になります。
– 手順
– 特定相談支援事業所と契約
– 面接・家庭訪問等でアセスメント(生活状況、課題、強み、学校での様子)
– 支援目標・利用頻度・併用サービス(児童発達支援や短期入所等)を整理
– 「障害児支援利用計画案」作成(保護者の同意を経て完成)
– 補足 自治体によっては保護者作成の「セルフプラン」も可とする運用がありますが、原則は相談支援専門員の関与が推奨されています。
ステップ4 市区町村へ受給者証の申請
– 申請先 市区町村役場(障害福祉・子ども家庭部門)
– 提出物(自治体によって異なるため目安)
– 申請書(障害児通所給付費支給申請)
– 障害児支援利用計画案(またはセルフプラン)
– 医師の意見書または診断書、各種手帳(療育手帳等)があればその写し
– 本人・世帯のマイナンバー、身分証、健康保険証
– 所得状況の確認書類(利用者負担上限月額の判定に必要)
– 事業所の候補(第1~第2希望程度)、希望曜日・送迎の要否
– 申請時のポイント
– 利用希望曜日・回数は現実的に。
空き枠と合致させるとスムーズ。
– 長期休暇中の利用時間(平日と異なる)も見込んで記載。
ステップ5 自治体の調査・審査・支給決定
– 市区町村は、提出資料や聞き取りに基づき、支援の必要性・相当性を審査します。
必要に応じて学校等からの意見聴取が行われることもあります。
– 決定内容(受給者証に記載)
– サービス種別(放課後等デイサービス 等)
– 支給量(1か月あたりの利用可能日数等)
– 支給期間(多くは6か月~1年。
更新時に見直し)
– 利用者負担上限月額
– 期間の目安 2~4週間程度が多いですが、繁忙期や書類追加があると1~2か月かかる場合も。
ステップ6 受給者証の交付
– 交付後は原本が手元に届きます。
記載事項(支給期間・量・上限月額)を必ず確認し、希望と異なる場合は相談支援専門員・自治体に早めに相談。
ステップ7 事業所との契約・個別支援計画の作成
– 契約時に必要なもの(目安)
– 受給者証(原本)
– 健康保険証、各種医療費助成受給者証(マル福等)
– 印鑑、緊急連絡先、学校情報
– 服薬情報、アレルギー情報、配慮事項
– 個人情報・送迎同意書等
– 重要事項説明 利用料の考え方(1割負担・上限月額)、加算・自費オプションの有無、欠席連絡・キャンセルポリシー、行事費等の実費、事故時の対応、苦情解決制度など。
– 個別支援計画(事業所作成)
– 児発管がアセスメント(面談・観察)を行い、具体的な目標・支援内容・評価方法・期間を設定。
保護者と合意形成。
– 学校や相談支援と協働し、合理的配慮や一貫性のある支援設計を整える。
ステップ8 利用開始・運用
– 初回利用までに、送迎ルート・時間、連絡方法、持ち物、食事・おやつの扱い、課題への優先順位などをすり合わせ。
– 利用開始後
– 相談支援専門員によるモニタリング(概ね6か月に1回)で計画の妥当性を継続確認。
– 支給決定の更新時期(受給者証の有効期間満了前)に、再度計画見直しと申請。
– 学校の学期・学年の変わり目、生活環境の変化(転居・転校等)で必要に応じ変更申請。
スケジュール例(モデルケース)
– 週0 自治体・相談支援へ初回相談、事業所の情報収集開始
– 週1~2 2~3事業所を見学・体験、相談支援と契約・アセスメント
– 週2~3 障害児支援利用計画案が完成、市区町村へ申請
– 週4~6 自治体審査・支給決定、受給者証交付
– 週6~8 事業所と契約・個別支援計画作成・利用開始
繁忙期(年度末・年度初め)は余裕をもって早めの着手がおすすめです。
よくある質問・つまずきポイント
– 診断書がないと申請できない?
– 自治体運用に差があります。
医師の意見書・診断書や、学校・関係機関の意見が求められることが多いですが、必ずしも手帳保有が必須ではありません。
まずは相談を。
– 相談支援(計画相談)は必須?
– 原則、障害児支援利用計画(案)の提出が求められ、専門職の関与が推奨されています。
やむを得ない事情でセルフプラン可とする自治体もありますが、支給決定の適正化・サービス間連携のため、相談支援の活用が一般的です。
– 何回通える?
– 支給決定の「支給量」で上限が決まります。
希望より少ない決定となる場合は、アセスメント情報の充実、学校・関係機関の意見書の添付、生活上の必要性の具体化が鍵になります。
– 費用はいくら?
– 原則1割負担。
ただし所得に応じた「負担上限月額」が設定され、その範囲内での負担となります。
おやつ・行事費・教材費等の実費は別途。
– 引っ越し(転入)時は?
– 新住所地で改めて手続きが必要(受給者証の切替)。
余裕を持って相談支援・自治体に連絡。
手続きの根拠(法令・通知・制度)
– 法律(根幹)
– 児童福祉法 障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援等)の位置づけ、市町村による支給決定・受給者証の交付、相談支援の枠組み等が規定されています。
– 関連政省令(児童福祉法施行令・施行規則等) 申請様式、支給決定手続、事業所の人員・設備・運営基準などの詳細を定めています。
– 厚生労働省の通知・ガイドライン
– 障害児通所支援の支給決定や運用に関する通知、事業所運営の留意事項、相談支援の実施要領等が示されています(例 障害児通所支援に関する手引き、支給決定の適正化に関する留意事項通知等)。
– 2018年以降の制度整備で、障害児支援利用計画(案)の提出を原則とする運用が周知され、支給決定のプロセスで相談支援の関与が重視されています。
– 利用者負担の考え方
– 児童福祉法に基づく障害児通所支援は、原則1割負担+所得に応じた月額上限という仕組みで、上限額は国の基準に基づき世帯所得階層ごとに設定されています(自治体の窓口で上限額が記載された受給者証が交付されます)。
– 受給者証の性質
– 市町村が法令・通知に基づいて支給決定を行い、その内容(サービス種別・支給量・期間・負担上限額)を記す公的な証明が「障害児通所受給者証」です。
これが契約・請求の根拠となります。
実務に役立つコツ
– 見学は複数箇所へ お子さんの特性と事業所の得意分野(学習支援、SST、感覚統合、運動、余暇支援等)のマッチングを重視。
– 学校と早めに連携 担任・コーディネーターに事情を共有し、学校の配慮と放デイの支援がつながるように。
– 申請書の「必要性」は具体的に 放課後の困りごと(安全確保、社会性、居場所確保、保護者就労等)を具体例で伝える。
– 更新の見通し 受給者証の有効期限の2か月前を目安に、相談支援へ連絡して評価・計画の更新準備を。
まとめ
– 放デイ利用開始までの要は「相談支援による計画づくり」と「自治体への支給申請」。
見学・体験で適合する事業所を見極め、相談支援専門員と一緒にお子さんに合った目標・通所頻度を整理すると、支給決定がスムーズです。
– 法的には児童福祉法とその下位法令・厚生労働省通知に基づく制度で、受給者証の交付により、負担上限月額・支給量・期間が明示されます。
契約後は事業所の個別支援計画に沿って利用が始まり、6か月ごとのモニタリングと定期更新で質を保ちます。
– 具体の提出書類や審査の運用は自治体差があるため、必ずお住まいの市区町村窓口と相談支援事業所で最新の要件を確認してください。
注意 本稿は一般的な流れを解説したもので、法的助言ではありません。
個別の事情(医療的ケア、転居、きょうだいの同時利用等)がある場合は、早めに自治体・相談支援・事業所へご相談ください。
個別支援計画はどのように作成し、相談支援専門員や学校・医療とどう連携すればよいのか?
ご質問ありがとうございます。
放課後等デイサービスにおける「個別支援計画(ISP)」の作成手順と、相談支援専門員(計画相談/障害児相談支援)、学校、医療との実践的な連携方法を、根拠(法令・ガイドライン)とあわせて詳しく解説します。
現場の運営・加算・監査対応や質改善(PDCA)にそのまま使えるよう、ステップとチェックポイントを具体的にまとめています。
用語整理(役割の違い)
– 個別支援計画(ISP) 通所事業所(放課後等デイサービス)が作成し、事業所内での支援や関係機関連携を具体化する計画。
児童発達支援管理責任者(児発管)が中心となって策定・モニタリング・見直しを行う。
– 障害児支援利用計画(案)(計画相談) 相談支援専門員が作成し、市町村の支給決定(受給者証)やサービス量・全体目標の根拠となる上位計画。
事業所の個別支援計画は、この内容と整合させる。
– 学校の個別の教育支援計画/個別の指導計画(IEP等) 学校が作成。
学習・行動・自立活動等の教育上の目標と支援方針。
適切な同意のもと整合を図る。
– 医療・療育の計画・指示 主治医の診療情報、療法士(PT/OT/ST)等のプログラム・ホームエクササイズ等。
安全管理や一貫性の鍵。
個別支援計画の作成ステップ(PDCA)
A. 事前準備と契約・同意
– 受給者証、障害児支援利用計画(案)、既往歴・投薬・アレルギー、緊急連絡体制を確認。
– 情報共有に関する同意書(学校・医療・相談支援との三者・多者間連携に関する同意)を取得。
個人情報保護法に従い、目的・範囲・期間を明示。
– リスクアセスメント(医療的ケア、てんかん、重度アレルギー、行動上の危険、送迎時リスク等)を先に把握。
B. アセスメント(多面的・強み志向・ICF視点)
– 本人・家族の意向聴取(困り・やりたいこと・価値観・将来像)。
子どもの意思表明を年齢・特性に応じて工夫(選択肢提示、視覚支援等)。
– 発達・行動・生活アセスメント
– 観察(自由遊び・集団活動・課題場面)、ABC記録(先行条件-行動-結果)。
– 検査・尺度(ある場合) WISC、新版K式、Vineland、S-M社会生活能力、感覚プロファイル、CARS2、PEP-3等。
学校の評価(観点別評価やIEP)も参照。
– 生活機能(ICF-CY) 心身機能・活動・参加、環境因子(家庭、学校、地域資源、合理的配慮の状況)。
– 環境調整ニーズ(視覚構造化、スケジュール、課題の分化、感覚過敏への配慮、コミュニケーション手段)。
– 強みの明確化(興味、得意、成功体験の条件)。
PBS(ポジティブ行動支援)の基盤に。
C. 目標設定(SMART+参加志向)
– 長期目標(6〜12か月) 参加の姿(学校・家庭・地域)に結びつく表現で。
例)学級活動での発表に月1回挑戦し、自信につなげる。
– 短期目標(1〜3か月) 具体・測定可能・達成基準・期限付き。
例)週2回の活動で、支援者のプロンプト1回以内で順番待ちを2分保持できる。
– 合理的配慮・環境調整目標も併記(行動変容だけに偏らない)。
D. 具体的支援計画(介入内容・頻度・役割)
– 介入の方法 構造化、視覚支援、タスクアナリシス、逐次的フェイディング、社会的スキルトレーニング、感覚調整、言語・コミュニケーション支援、学習支援、就学・進学移行支援、家族支援(ペアレントトレーニング等)。
– 提供頻度・時間・担当者を明記(曜日、個別/小集団、1回の時間、実施者資格)。
– リスク対応計画 発作時・アナフィラキシー・行動危機時の具体的手順、連絡体制、避難計画。
– 家族支援 家庭での再現可能な工夫、ホームプログラム、連絡帳・ICT活用の方法、相談窓口。
– 連携計画 相談支援、学校、医療それぞれに「誰に・何を・いつ・どの媒体で」情報共有するか。
E. 合意・周知・実施
– 計画書の説明 本人・保護者にわかりやすく説明し、同意・署名。
必要に応じて概要版やピクト版を本人向けに作成。
– 事業所内共有 全職員に計画の要点を周知。
勤務形態に応じて引継ぎ様式を整備。
F. 記録・モニタリング・見直し
– 実施記録 目標ごとに達成度、支援方法、反応、次回への示唆を簡潔に。
指標は定量(回数・秒数・割合)+定性(質的変化)。
– ミニレビュー 毎月など定期的に傾向を可視化(グラフ化)し、支援方法を微修正。
– フォーマル見直し 原則6か月ごと(必要時は随時)。
相談支援専門員と情報共有し、関係機関連携会議で整合。
相談支援専門員との連携(計画相談の要)
– 初期段階
– 支援利用計画(案)の共有 上位目標・支給量・利用調整・家族の意向を確認。
– サービス担当者会議 新規・更新時に開催。
事業所からアセスメント結果・個別支援計画(案)を提示し、整合性をとる。
オンライン活用可。
– 実施・モニタリング
– 月次・四半期の進捗共有 到達度、課題、家族状況変化、追加支援ニーズ。
相談支援側のモニタリングシート様式に合わせると効率的。
– 変更時の臨時会議 行動危機、医療リスク変化、学校での大きな課題、進学・卒業・長期休暇対応など。
– 役割分担の明確化
– 相談支援 全体コーディネート・資源開拓・権利擁護・サービス量調整。
– 事業所 日々の支援実装・エビデンス収集・具体的手立ての提案。
– セルフプランの場合
– 保護者計画でも、自治体の指導に沿い、必要に応じ相談支援への接続を提案。
計画の客観性確保が重要。
学校との連携(IEPとISPの整合)
– 情報共有の原則
– 保護者の文書同意を前提に、学校と双方向の情報共有。
目的・範囲・期間を限定。
– 担任、特別支援コーディネーター、養護教諭、通級担当など窓口を一本化。
– 共有する内容と方法
– 学校→事業所 個別の教育支援計画/個別の指導計画の目標・配慮事項、行動のトリガー、成功条件、合理的配慮の内容。
– 事業所→学校 アセスメント所見、効果のあった支援手立て(視覚支援の型、プロンプト段階、環境調整)、家庭での汎化結果。
– 手段 連絡帳、共有シート、合同ケース会議、授業参観や見学(学校の許可・同意に基づく)。
– 連携の着眼点
– 参加の一致(授業参加、昼休みの過ごし方、係活動、行事参加)。
学校活動の「参加」を最上位の成果指標に。
– 一貫性(事業所→家庭→学校で手立てがつながる)。
例 スケジュール提示の形式を統一。
– 合理的配慮の具体化(過剰な本人努力に依存しない)。
例 提出期限の調整、別室の一時退避場所の設定。
– 節目の支援
– 就学前→小学校、学年進行、進学・卒業の移行支援計画を、相談支援・学校・医療と合同で策定。
見学・体験・引継ぎ資料の標準化。
医療・療育との連携(安全・専門性の橋渡し)
– 情報の取得と共有
– 同意の上で、診療情報提供書、主治医の意見、服薬情報、アレルギー・発作プロトコル、療法士の指示・ホームプログラムを入手。
– 事業所の計画・進捗を定期的にフィードバックし、助言を受ける。
– 安全管理
– 医療的ケア児の場合は、配置基準・看護職の関与・緊急時手順(エピペン、吸引、痙攣時対応)を明文化・訓練。
– 服薬管理(ダブルチェック、記録、与薬権限)と保管・廃棄ルールの徹底。
– 支援の一貫性
– 療育(PT/OT/ST)の目標とISPの目標をそろえ、日常場面での汎化・反復を担う。
– 感覚調整や摂食嚥下など専門領域は、助言に基づき無理のない適応。
記録とエビデンス(監査・質改善に強い運用)
– 必須記録類
– アセスメント票、個別支援計画書、同意書(情報共有・医療連携)、実施記録、モニタリング記録、サービス担当者会議の議事録、リスクアセスメント、事故・ヒヤリハット報告。
– 指標化と見える化
– 目標ごとに定量化(例 遅刻回数、待機時間、SST課題達成率)+定性(授業参加の質、自己効力感の言動)。
– 月次でグラフ化し、家族・学校・相談支援へ共有すると、合意形成と資源調整が進む。
よくあるつまずきと回避策
– 目標が抽象的→SMART化し、達成基準と期限を必ず設定。
– 本人の声が薄い→選択式面接や写真・絵カードで意思表明の機会を増やす。
– 事業所内での属人化→計画の要点を1枚にまとめ、全職員に配布・掲示(個人情報配慮)。
– 連携の断絶→定期共有の期日・媒体を計画書に組み込む(誰が・何を・いつ)。
根拠(法令・ガイドライン等)
– 児童福祉法および関係省令
– 指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令) アセスメントの実施、個別支援計画の作成・説明・同意、定期的見直し(おおむね6か月ごと)等を規定。
– 児童福祉法施行規則 運営・記録に関する各種要件。
– 厚生労働省ガイドライン・通知
– 放課後等デイサービスガイドライン(2017策定、以後改訂) ICF視点のアセスメント、PDCA、家族支援、関係機関連携、自己評価・事業所評価等を明記。
– 児童発達支援ガイドライン 放デイと共通する質の確保・向上の枠組みを提示。
– 計画相談支援・障害児相談支援に関するガイドライン サービス担当者会議、モニタリング、上位計画と事業所計画の整合性を明示。
– 医療的ケア児支援に関する通知・Q&A 看護職の配置、緊急時対応、リスク管理。
– 学校との連携に関する根拠
– 文部科学省「個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成と活用に関する手引」等 校外機関連携と保護者同意の重要性、合理的配慮の具体化。
– 学校教育法等 教育的支援の枠組み、個別最適な学び・合理的配慮の考え方。
– 個人情報保護
– 個人情報の保護に関する法律 第三者提供には本人(保護者)同意が必要。
目的明確化・最小限共有の原則。
– 差別解消・合理的配慮
– 障害者差別解消法 合理的配慮の提供義務(行政機関等)と配慮の趣旨、関係機関連携の意義。
現場で使える簡易テンプレ(項目例)
– 基本情報 氏名、学年、受給者証情報、主治医・学校・相談支援の連絡先。
– 本人・家族の意向 やりたいこと、困り、将来像。
– アセスメント要約 強み、課題、環境因子、医療安全。
– 長期目標(6–12か月)と短期目標(1–3か月)+達成基準・期限。
– 具体的支援 方法、頻度、担当、使用教材・支援機器。
– 環境調整・合理的配慮 視覚支援、休憩、感覚配慮、避難計画。
– 家族支援 ホームプログラム、連絡方法、相談窓口。
– 連携計画 相談支援・学校・医療へ、何を、誰が、いつ、どう伝えるか。
– 評価・見直し予定 月次レビュー、6か月見直し日、担当。
– 同意欄 保護者署名、情報共有同意の範囲・期間。
まとめ(実践ポイント)
– ISPは「本人の参加」を最上位に据え、SMART目標と具体手立てを明記。
– 相談支援の上位計画と必ず整合させ、担当者会議で合意形成。
– 学校IEP・医療計画と「一貫性」を作り、家庭での汎化を支える。
– 計画は説明・同意・周知・実施・記録・見直しのPDCAで回す。
– 法令・ガイドラインに沿った記録と同意管理で、質とコンプライアンスの両立を。
補足
– 具体的な様式・運用は自治体の指導・監査実務や最新通知で差異があります。
最新の厚労省通知、自治体実施要綱、文科省手引の改訂版を随時確認してください。
– 医療的ケアや高度な行動支援が必要な場合は、看護職・専門職の配置や外部専門家の助言体制を早期に構築してください。
以上を踏まえ、個別支援計画は「本人・家族の願いを中心に」「関係機関連携で一貫性を持って」「測定可能な成果で」設計・運用すると、子どもの参加と成長が加速し、学校・家庭・地域での生活の質が着実に向上します。
事業所選びで失敗しないために、見学時のチェックポイントや比較のコツは何か?
放課後等デイサービス(以下「放デイ」)や障害児相談支援の事業所選びは、子どもの発達や家族の暮らしに直結します。
見学は「雰囲気を見る」だけでは不十分で、支援の質・安全性・法令遵守・連携体制まで具体的に確認する場です。
ここでは、失敗しないための見学チェックポイントと、複数事業所を比較するコツを、実務・制度の両面から詳しく解説します。
あわせて、根拠となるガイドラインや法令の考え方も示します。
見学前の準備(成功の7割はここで決まる)
– 子どものニーズの言語化
– 例)集団が苦手でトラブルが多い→SSTやポジティブ行動支援が必要
– 微細運動が弱い→作業療法的アプローチや感覚統合の要素があるか
– 宿題サポート重視→学習支援の体制・学校との連携の有無
– 優先順位の設定(送迎・曜日・専門性・費用・定員などの優先度を3つに絞る)
– 相談支援専門員と事前すり合わせ
– サービス等利用計画のゴール(半年〜1年)と、事業所に求める役割を整理
– 事前情報の収集
– 事業所の自己評価(保護者等向け)の公表、活動内容、対象特性、実費、送迎範囲
– 見学の時間帯
– 実稼働時間(放課後の賑わい)に見学予約。
平日と長期休暇で雰囲気が変わるため、可能なら両方確認
見学時のチェックポイント(カテゴリ別)
A. 安全・法令遵守・運営体制
– 入口の施錠・入退室管理、引き渡し確認の徹底
– 事故・ヒヤリハットの記録と再発防止の仕組み(職員間で共有されているか)
– 避難経路・消火器・AEDの設置、避難訓練の実施頻度と記録
– 感染症対策(手指衛生・換気・消毒・体調確認動線)
– 重要事項説明書、苦情解決の体制(第三者委員・連絡先)を見せてもらえるか
– 虐待防止の指針・研修の実施状況、ハラスメント相談の窓口
– BCP(業務継続計画)の整備と訓練の有無(災害・感染症時の運営方針)
– 情報公開の姿勢(自己評価結果の掲示、ウェブでの公表)
B. 人員配置・専門性・研修
– 管理者・児童発達支援管理責任者(児発管)の勤務形態(常勤・専任か、現場にいる時間)
– 児童指導員・保育士等の資格構成、経験年数のバランス
– 強度行動障害支援者養成研修、医療的ケア児対応、救命講習などの研修受講状況
– 職員の定着度(離職が多すぎないか)、チームとして落ち着いた雰囲気か
– ボランティアや学生アルバイトの位置づけ(過度に依存していないか)
C. 支援内容・計画・評価(PDCA)
– アセスメント→個別支援計画→支援→モニタリング→見直しの流れが明確か
– 目標はSMART(具体・測定可能・達成可能・関連・期限)になっているか
– 具体的な評価方法(行動記録、観察記録、尺度活用、到達度の可視化)
– 保護者へのフィードバック方法(連絡帳・面談・動画共有等)と頻度
– 活動の根拠(SST、視覚支援、構造化、ポジティブ行動支援、感覚プロファイル等)を職員が説明できるか
– 宿題支援や学習支援は、単なる見守りでなく方法論があるか(タイムスケジュール、プロンプト、強化の設計)
D. 環境・構造化・感覚配慮
– 視覚的スケジュール、活動の予告、ルール掲示、トークン等の視覚支援
– 静と動の切り替え、クールダウンスペースの確保、音・光・匂いの配慮
– 遊具・教材が子どもの発達段階に合い、安全に配置されているか
– 集団活動と個別の時間のバランス、過密でないか(定員と実利用人数の比)
E. 行動支援・危機対応
– 問題行動の捉え方が非罰的で、予防・環境調整・代替行動の学習を重視しているか
– ABC記録や機能的アセスメントの実施、保護者と一貫した対応を取る仕組み
– 身体拘束等の禁止・最小化に関する明確な指針と職員の理解
F. 連携・家族支援
– 学校・療育機関・主治医・相談支援専門員との情報連携(同意・記録)
– 面談の設定、ペアレントトレーニングや保護者会の有無
– 兄弟・家族の負担軽減に配慮したスケジューリングや情報提供
G. 送迎・医療的対応・緊急時
– 送迎の引き継ぎ方法、ルートの無理のなさ、車両の安全(チャイルドシート等)
– 薬・アレルギー・てんかん等への対応手順と、職員が即答できるか
– 緊急時の連絡体制(複数連絡先、手順の標準化)
H. 利用者層・雰囲気・子どもの反応
– 年齢層・特性の構成、相性の見立てをしてくれるか
– 子どもたちの表情、主体的に参加できているか、過度な待ち時間がないか
– 職員の声かけが肯定的・具体的で、予告や選択肢提示があるか
I. 費用・契約・透明性
– 受給者証の自己負担上限の説明、加算・実費(おやつ・教材・外出費)の明細
– 欠席時対応や振替のルール、キャンセルポリシー
– 契約前に重要事項説明書・運営規程を持ち帰って検討可能か
比較のコツ(情報を「見える化」して迷いを減らす)
– 同条件で比較
– 同じ曜日・時間帯で複数見学。
長期休暇中も可能なら確認
– チェックリスト化とスコアリング
– 上記カテゴリを5段階で採点+メモ。
合計点よりも「優先3項目」での強さを重視
– トライアル利用と子どもの声
– 体験利用で「帰宅後の様子」「翌日の行きしぶり」「睡眠・食事の変化」を観察
– 子どもが表現しやすい質問で感想を聞く(楽しかった点、困った点、また行きたいか)
– 第三者の意見
– 相談支援専門員、学校の担任・コーディネーター、医療・療育機関の意見を参照
– 書類で裏どり
– 自己評価結果(保護者等向け)の公開内容、改善計画、苦情件数と対応を確認
– 乗り換え・併用の設計
– 合わない場合の見直し時期をあらかじめ決める(例 3か月後にモニタリング)
– 目的によって併用(例 平日は学習特化、土曜はSST特化)も検討
よくあるつまずきと回避策
– 送迎の便利さだけで決めてしまう
– 回避 支援の中身と安全体制を最低限満たしていることを優先
– 楽しい活動が中心で、目標が曖昧
– 回避 個別支援計画の目標と評価方法を具体的にもらう
– 人手不足・過密で個別対応が薄い
– 回避 実利用人数、支援の手厚さ、待ち時間の少なさを現場で観察
– 実費や加算の理解不足
– 回避 費用の内訳と根拠、欠席時の扱いを契約前に書面で確認
根拠・背景(なぜ上のポイントが重要か)
– 法令・基準の観点
– 児童福祉法および関係省令・告示に基づき、放課後等デイサービスには人員配置、設備、安全管理、虐待防止、苦情解決、情報公開、自己評価の実施等が定められています。
見学でこれらの運用実態に触れることが、法令遵守と質の確認につながります。
– 厚生労働省の「児童発達支援ガイドライン・放課後等デイサービスガイドライン」(初版2017、以降の報酬改定に合わせて見直し)では、アセスメントに基づく個別支援計画、保護者・学校との連携、評価と改善(PDCA)、虐待防止、緊急時対応、自己評価結果の公表等が求められています。
チェックリスト化して確認することは、ガイドラインの趣旨に沿います。
– 近年の報酬改定ではBCP(業務継続計画)の整備や虐待防止体制・研修の強化が義務化・重点化されました。
災害・感染症時の運営や安全確保は、事業所の成熟度を映す重要指標です。
– エビデンスに基づく支援の観点
– 構造化(活動の見通しや環境調整)、視覚支援、社会的スキル訓練(SST)、ポジティブ行動支援(PBS)、機能的アセスメントに基づく介入は、発達特性のある子どもへの有効性が国際的にも国内でも支持されています。
現場での実装は、職員が根拠や手順を説明でき、記録・評価が運用されているかで判別できます。
– 支援の効果は「一貫性」が鍵。
家庭・学校と連携し、同じ合図・同じ約束・同じ強化子を共有するほど、般化と定着が進むとされます。
見学時に連携の仕組みを確認するのは、このエビデンスに沿う行為です。
– 透明性・第三者性の観点
– 自己評価(保護者等向け)の公表は、PDCAと説明責任の実践です。
改善課題が明確で、翌年度の取り組みに反映されている事業所は、質の向上が期待できます。
– 苦情解決や第三者評価(自治体制度)を活用しているかは、組織の開かれた姿勢の目安になります。
見学で使える質問例(持参メモ推奨)
– 子どもの現状に近いケースで、どのようなアセスメントと支援を行い、どんな変化があったか具体例は?
– 個別支援計画の目標設定は誰がどのように行い、達成度はどう測っていますか?
面談はどの頻度ですか?
– 問題行動が起きたときの基本方針と、予防・代替行動の教え方の手順は?
– 学校との連携はどう進めていますか?
連絡方法と頻度、行事や合理的配慮との橋渡しは?
– 職員研修の最近のテーマは?
強度行動障害、医療的ケア、虐待防止、救命講習の受講状況は?
– 送迎の安全管理(乗降時チェックリスト、遅延時の連絡、車内置き去り防止)の仕組みは?
– 実費の内訳と上限、欠席・振替のルール、長期休暇中の追加費用は?
– 自己評価結果の主要な改善点と、今年度の具体的な取り組みは?
まとめ(決め手は「目的適合×安全×一貫性」)
– 子どもの目的に合う専門性があるか
– 安全・法令遵守の基盤が強固か
– 家庭・学校と一貫した支援ができる体制か
この3条件がそろう事業所は、長期的に見て満足度が高く、子どもの成長につながりやすい傾向があります。
最終的には、子ども本人の反応と、保護者として「ここなら任せられる」という安心感も大切にしてください。
契約後も定期的に振り返り、必要であれば相談支援専門員と計画を見直しましょう。
注意 人員配置や算定要件等の細部は年度の報酬改定や自治体運用で異なることがあります。
最新情報は各自治体の指定基準通知や事業所の重要事項説明書でご確認ください。
【要約】
放課後等デイは、学齢期の障害児に療育・生活訓練・余暇・学習補完・外出等の直接支援を事業所で提供(送迎や看護体制あり)。相談支援は、家族のニーズ把握から計画作成・調整・会議・モニタリング・危機対応・移行支援までを担う計画相談。両者は児童福祉法に基づき、市町村の受給者証で利用。放課後・長期休暇に2〜3時間程度通所。相談支援は面接や会議を適宜実施、未就学も対象。
オーパコラム vol.1
オーパ利用についてはお気軽にお問合せください。